学習型IoTアルコールチェッカー TISPY2(ティスピー ツー)
去る3月6日(火)、マイドームおおさかで45名の参加を得て開催された「具体的事例で学ぼう! 知っておきたい模倣デザイン対策」では、中小企業やデザイナー向けに、模倣品に対してどんな知財対策があるのか?、どうすれば有効な知財が取れるのか?などについて、古谷国際特許事務所 弁理士の松下 正 氏に、具体的事例を用いて分かりやすく、ストーリー仕立てでご説明いただきました。

◆シーン1 会社Xは、デザイン会社Yに頼んで、商品を発売したが、半年後、中国から模倣品が出てきた。会社Xは、デザイン会社Yに相談。デザイン会社Yは自社で作ったデザインなので、著作権で対応できると考え、専門家に相談した。 さてどうなるのか?
原則、応用美術品は著作権では保護されない。
(応用美術品=美術作品を実用品に応用したもの・いわゆる一般的な量産品)
参考判例:ぬいぐるみ形態模倣事件→著作権による保護を受けられない。
しかし、稀ではあるが応用美術品で著作権を認められたケースもある。
参考判例:TRIPP TRAPP事件→著作権による保護を認めた。
そっくりのコピー商品は、不正競争防止法の取り締まり対象である。
あるいは、模倣品が販売開始から3年以内の商品と実質的に同一の形態であること。(不競法2条1項3号)
参考判例:タオルセット事件→ほぼ同一の形態であるとして、不正競争防止法の対象とした。
まとめ
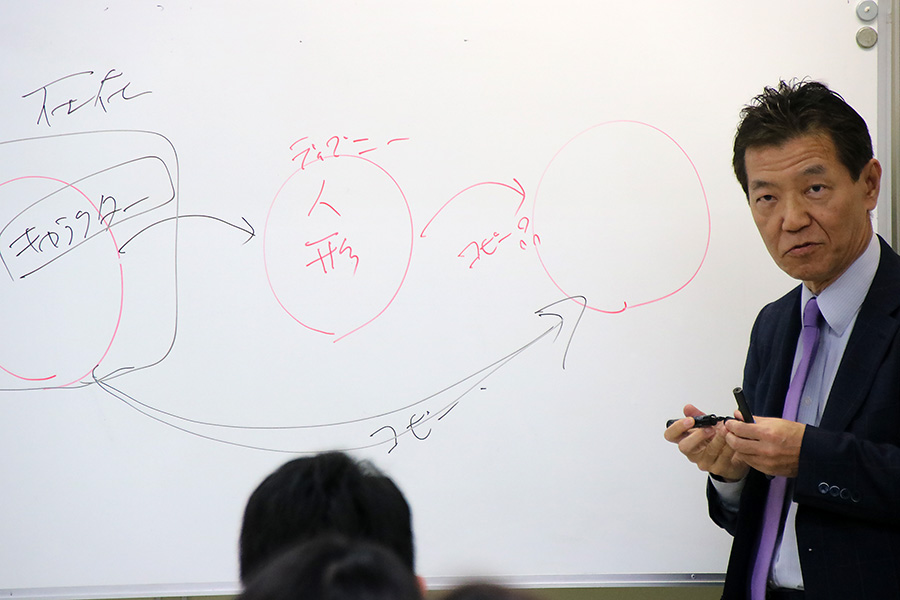
◆シーン2
会社XはデザイナーYにイラストを依頼し、そのイラストをカタログの表紙に使用していた。会社Rから「自社のイラストと似ているので著作権侵害である」と警告がきた。
たしかに、似ているようにも思えるが、どのくらい似ているとダメなのか?
・デッドコピーでなくても著作権侵害となる場合あり。
・翻案(=翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的な表現形式を変更して新たな著作物を創作する行為)
・オリジナルの本質的特徴を直接感得できるか?
参考判例:博士イラスト事件→きわめてありふれたもので表現上の創作性がなく、本質的特徴を直接感得できない。
参考判例:立体イラスト事件→一部の特徴的な表現について創作性が認められ、本質的特徴を直接感得できる。
まとめ
<大阪府:フューチャーベンチャーキャピタル株式会社>
女性のための創業セミナー
〜あなたらしく生きるための選択肢〜
このたび、大阪府はフューチャーベンチャーキャピタル株式会社と共催で、起業に関心をお持ちの女性を対象に創業セミナーを開催します!
起業をして自分でビジネスをはじめたい。でも、ビジネスを立ち上げるのは、なんだかすごく難しそう。実際、何から手をつければよいのか、わからない。
わからないがために、なんとなく、「起業は自分には遠い存在」だとは思っていませんか。
本セミナーでは、起業に精通した講師と先輩女性起業家からの講義を通じて、そんな悩みを解消するお手伝いをします!
起業は決してハードルが高いものではありません。自分の夢を叶えるため、今こそ起業について理解を深めてみませんか。多くの方のご応募、お待ちしております!
■日時 平成30年3月20日(火)
第一部プログラム 14:00〜16:00(13:50〜 受付開始)
第二部プログラム 18:00〜20:00(17:50〜 受付開始)
※両方同じ内容です。ご都合の良いプログラムにご参加ください。
■場所 大阪信用金庫 日本橋ビル7階 (大阪市中央区島之内2-15-20)
最寄駅:近鉄日本橋駅、地下鉄堺筋線・千日前線 日本橋駅
■登壇者 (講演)
高橋 秀昭 氏(フューチャーベンチャーキャピタル株式会社)
仙田 忍 氏(株式会社ルカコ 代表取締役)
(パネルディスカッション)
高橋 秀昭 氏(フューチャーベンチャーキャピタル株式会社)
仙田 忍 氏(株式会社ルカコ 代表取締役)
金子 洋子 氏(株式会社ロカロジラボ 代表取締役)
嶋 都支子氏(株式会社micia luxury 代表取締役)
■定員 30名(先着順)
■費用 無料
■内容・申込み こちらのURLをご確認ください。
■問合せ フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
TEL:075-257-6656(※平日9:00〜17:00)

価値は意味から、意味は関係性から生まれる『構想設計革新イニシアティブキックオフシンポジウム』
技術革新やグローバル化の流れの中で社会や市場が変化し、「顧客価値の高い製品・システム・サービスで顧客や社会の未来に寄り添い、事業創成や市場開拓に繋げたい」という事業者のニーズが益々高まっています。また、「自己の存在価値を高め、高いモティベーションで、チャレンジングな未来に能動的に関わる」という働き方変革も望まれています。
しかし、従来の構想設計では「会議が非効率で時間が足りない」、「感覚や地理感の相互理解が不十分で深い議論が出来ない」、「上下関係や立場の違いで意見や提案が出しにくい」、「決定事項に納得感がなくモティベーションが低い」等の具体的な問題があり、(国研)産業技術総合研究所では、その解決に資する研究開発を国家プロジェクト「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」等で行ってきました。
これらの研究成果を軸に、「構想設計というツールで組織や市場のイニシアティブを取る」同志を募り「手法や道具を見直し、組織の壁を超えて協業を加速する」革新を起こしたいという思いで構想設計革新イニシアティブを立ち上げるための『キックオフシンポジウム』を実施します。
これまで大阪府、(公財)大阪産業振興機構及び(一社)DCCでは「おおさか地域創造ファンド」を活用し、全国的に広がる「地域産業」×「デザイン」の枠組み支援をいち早く取り入れ中小企業とデザイナー・クリエイターをマッチングさせて、高付加価値で収益性の高い事業プロジェクト支援を取り組んできました。(=「大阪デザインイノベーション創出コンペティション(DIMO)事業」)
今後も大阪で、このような取組みが増えることを願い、次に継承するべく、「Design Innovation OSAKAミーティング」を開催します。過去の支援した高付加価値なプロジェクトの企業とクリエイターの代表メンバーが登場し、ブランドづくりや商品作り。そして、自社でのデザインイノベーションについて語ります。また、後半では新規事業の資金調達やファン作りに重要となる、台頭著しいクラウドファンディングの代表メンバーに登壇いただき、DIMOコーディネーターと共に、今後のデザインイノベーションについて考えてまいります。是非、ご参加ください!
大阪府、(公財)大阪産業振興機構及び(一社)DCCでは、「おおさか地域創造ファンド」を活用し、自社製品や技術等を用いて新たな高付加価値製品・サービスの開発を目指す中小企業とそれらの開発アイデアを提供できるデザイナー・クリエイターをマッチングさせることで中小企業の「デザインイノベーション」を推進する「大阪デザインイノベーション創出コンペティション事業」を実施しています。
今回、その一環として、経営におけるデザイン価値の観点から企業に関わり、企業の経営基盤を盤石なものにしてきた経営コンサルタント 乘松氏をお招きし、「経営とデザイン」をテーマとしたセミナーを開催します。
“デザイナーを迎えるための組織構築とは?” “メリット・デメリットは?”等、企業とデザイナーがうまく付き合うためにはどのような準備が必要なのかお話いただきます。
企業の皆さまには、デザイナーと仕事をする前にやるべきことについて、デザイナー・クリエイターの皆さまには、経営知識や経営戦略を理解しているデザイナーになるための指針を得ることができる内容となっています。この機会に是非、ご参加ください。
【日 時】平成30年2月7日(水)16:00~18:00
【場 所】マイドームおおさか 4階 セミナー室・会議室2(大阪市中央区本町橋2番5号)
【講 師】F.M.S Ltd. 乘松 尚 氏
【対 象】中小企業経営者、商品企画担当者、デザイナー 等
【定 員】20名(先着順)
【受講料】無料
【申込み】以下URLよりお申込みください。
https://dcc-net.biz/form/fms/9e15d15492
【主 催】一般社団法人 DCC
【後 援】ODCC(大阪デジタルコンテンツビジネス創出協議会)
【協 力】大阪府
【問合せ】DIMO事務局(一般社団法人 DCC) TEL:06-4792-8205 E-mail:info@dimo.osaka.jp
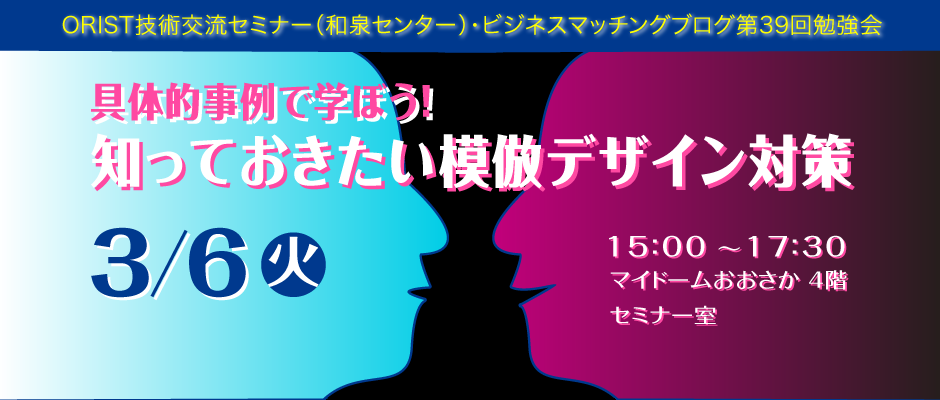
ORIST技術交流セミナー・ビジネスマッチングブログ【BMB】第39回勉強会
モノ余りの時代でも、差別化された商品・サービスは売れています。わかりやすいのはApple製品です。これは、他社商品とは一線を画したデザインがなされているからです。ただ、商品がヒットすると模倣品が出てきます。
本セミナーでは、模倣品に対してどんな知財対策があるのか、どうすれば有効な知財が取れるのかなどについて、具体的事例を用いてストーリー仕立てで説明いたします。
まだ会員でない方も是非ご参加ください。皆様のお越しをお待ちしております。
日 時:平成30年3月6日(火)15時から17時30分
会 場:マイドームおおさか 4階・セミナー室(大阪市中央区本町橋2-5)
定 員:40名(定員に達し次第、締め切らせていただきます。)
講 演:「具体的事例で学ぼう! 知っておきたい模倣デザイン対策」(120分)
古谷国際特許事務所 弁理士 松下 正 氏
講師プロフィール:古谷国際特許事務所所属。1991年弁理士登録。
得意分野は、ソフトウエアに関する知的財産(ビジネスモデル特許出願、侵害対応、コンピュータプログラムの著作権、画面意匠など)。
2017年日本弁理士会技術標準委員会委員長。
2009年日本弁理士会ソフトウエア委員会委員長。
2014年日本弁理士会近畿支部知財普及・支援委員会委員長などを歴任。
主な著書に「知って得するソフトウエア特許・著作権」(アスキー出版)、「インターネットの法律問題(-理論と実務-)」など。
BMB会員の皆様、あけましておめでとうございます。
BMB事務局(大阪府産業デザインセンター)の川本です。
去る12月19日、「ニューラルネットワーク・機械学習のしくみと産業活用」をテーマに行われたORIST&BMB第38回勉強会は、46名の参加を得て盛況に開催することができました。
遅くなりましたが、ここに開催報告をさせていただきます。
基調講演:「ニューラルネットワークの基礎とMATLAB®を使った予知保全/故障予測」
MathWorks Japan アプリケーションエンジニア部 井上道雄 氏

MathWorks社が開発するMATLAB(数値解析ソフトウェア)には様々な機能があるが、今回のセミナーでは、機械がいつ故障するかということを予測させ、AIが予知保全にも使えるという事例により、プログラマー以外の人達にもプログラマーが得ているメリット(自動化、機械学習など)を感じていただけるようにしたいという主旨の内容でした。
講演で受けたMATLABの印象は、顧客視点で現場の使いやすさを第一に考えており、システム構築する上での機械学習以外の要素に対する重要性とMATLABのサービスについての話も印象に残りました。
また、講師の井上氏は率直に機械学習の向き不向きや使いどころなどを話されており、実際のデモと合わせて機械学習の現在の状況をこれ以上期待できないほど身近に感じることができたように思います。
機械学習の活用事例
最初に人のまばたきを検知するデモが行われました。そのデモで示されたことは、機械学習とは過去のデータを使い、何らかの仕組み・傾向を自動で抽出できるようにするアルゴリズムということです。
それと関連する有名な用語にディープラーニングがありますが、ディープラーニングは機械学習の1つの手法にすぎず、全てのものに対してディープラーニングがベストということにはならないという話でした。
機械学習を利用すべき場面
例として、画像からその人がヘルメットをかぶっているかどうかを認識させるプログラムを作るとします。手作業で条件を指定することも可能ですが、黄色いヘルメットを被っているのを判定するのに頭部のあたりが黄色いと条件を決めても、背景が黄色かったりするとうまくいかなくなる。つまり、条件を指定すると応用が効かない。
そういった場合に、[ヘルメットを被っている/被っていない]というたくさんの画像を用意して、自動でどのような特徴があるかを認識(学習)させる、これが機械学習の得意としているところです。
うまくいかない場合もあるが、うまくいくと非常に柔軟にいろんな状況に対して判断ができる仕組みを作ることができます。

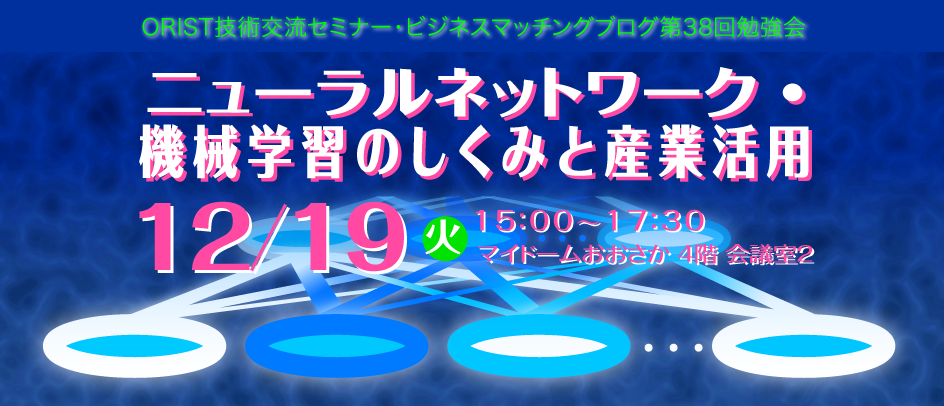
ORIST技術交流セミナー・ビジネスマッチングブログ【BMB】第38回勉強会
テーマ:「ニューラルネットワーク・機械学習のしくみと産業活用」
内 容:
近年、産業界でもAI(人工知能)への関心が高まっていますが、その仕組みをご存知でしょうか。
本セミナーのテーマとなっている「ニューラルネットワーク」は、人間の脳内にある神経細胞(ニューロン)とそのつながりを、人工ニューロンという数式的なモデルで表現したものです。
また「機械学習」は、人が事前に全ての動作をプログラムするのではなく、学習させたい内容を明示した上で、トレーニングによりAI自身が特定のタスクを実行できるようになることを指します。
本セミナーでは、皆様の関心事であるニューラルネットワーク等の仕組みを解説するとともに、MATLAB®による機械学習、さらに、(地独)大阪産業技術研究所の研究員による産業活用に向けたAI研究の具体的な成果を紹介します。
日 時:平成29年12月19日(火)15時から17時30分
会 場:マイドームおおさか 4階・会議室2(大阪市中央区本町橋2-5)
定 員:40名(定員に達し次第、締め切らせていただきます。)
公益財団法人大阪産業振興機構では、大阪府と連携し、『おおさか地域創造ファンド』重点プロジェクト事業として新たに「デザイン思考を導入した中小企業の商品・サービス開発支援事業」を実施します。
この事業では、平成19年度から平成28年度の間に『おおさか地域創造ファンド』に採択され助成事業を行った事業者の方を対象に、「事業戦略の再構築」を行うことで商品やサービスの売上増加につなげることを目的とした、ワークショップ形式の講座《中小企業デザイン開発思考cognition》を行います。
詳細は、下記サイトをご覧ください。
デザイン思考を導入した中小企業の商品・サービス開発支援事業 《中小企業デザイン開発思考cognition》受講生募集について
皆さんお待たせしました。先月7月25日(火)に開催された「ORIST技術交流セミナー・ビジネスマッチングブログ(BMB)第37回勉強会」その②は、Google金谷さんの講演報告です。
「モバイル検索ユーザーの増加に伴うGoogle検索の今、企業が取り組むべき課題とは!?」
グーグル株式会社 シニアサーチ・エヴァンジェリスト 金谷 武明 氏
キーワードはきちんとユーザーを見る
1. Googleとはどんな会社か Googleのミッションは
2. Googleの検索エンジンについて
ー検索の仕組みー
2.1 クロール(見にいって取得する)
2.2 インデックス(集めてきた情報を理解して整理する)
2.3 ランキング
3. サーチコンソールを使う
3.1 サイトのパフォーマンスを知る(Googleの検索に対して)
3.2 サイトの問題を知る
3.3 PCとモバイルを分けて分析する