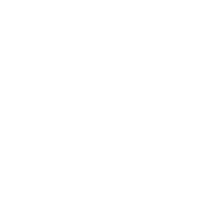つつした
BMB&MOBIOフォーラム(新春座談会)報告
- 2011/01/17 13:00
- 投稿者: kawamoto(oidc) カテゴリ:イベント報告
- 表示回数 4,685
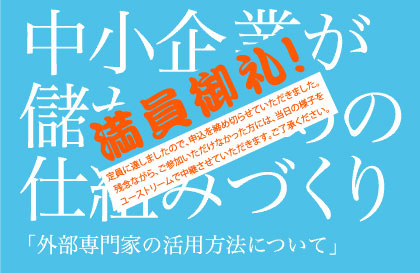
こんにちは。BMB事務局の川本です。
先日のBMB&MOBIOフォーラム(新春座談会)にお越しいただいた皆様、どうもありがとうございました。おかげさまで満席となった会場では75名(スタッフ含む)の方が熱心に耳を傾けて下さいました。
申込多数にてご参加いただけなかった皆様には、座談会の模様をユーストリームにてご覧頂けます。ご了承ください。
Ustream パネリストプレゼンの録画
http://www.ustream.tv/recorded/11966327
Ustream 座談会の録画
Ustream 座談会の録画
座談会の模様は上記のURLにてご覧頂けますが、ざっと概要をまとめまてみました。
BMBでは、今後も皆様のニーズにお応えするイベント、マッチングを実施して参ります。引き続き、ご支援の程よろしくお願いいたします。
パネリスト:
- 芦谷正人 DRIVE, Inc.代表(BMB会員)
- 中村尊裕 立命館大学・愛知江南短期大学客員研究員、合同会社デザインマネジメントファーム代表社員
- 高崎充弘 株式会社エンジニア代表取締役(BMB会員)
- 岩田浩司 adoria company代表、「With You LLP」メンバー(BMB会員)
- 下出 一 株式会社サピエンティスト代表取締役社長(BMB会員)
- 中島央雄 日本SYNコンサルティング株式会社代表取締役兼エグゼクティブビジネスプロデューサー(BMB会員)
 中島:今日の座談会は、株式会社エンジニア高崎社長の持論である、ものづくりプロセス「M:マーケティング」「P:パテント」「D:デザイン」「P:プロモーション」の軸で話を進行したい。
中島:今日の座談会は、株式会社エンジニア高崎社長の持論である、ものづくりプロセス「M:マーケティング」「P:パテント」「D:デザイン」「P:プロモーション」の軸で話を進行したい。その前に共通理解としてマーケティングとデザインの枠組みを捉えておきたい。まずデザインとは何か?
 芦谷:例えば、花王のクイックルワイパーというモップは3つのパーツに分かれている。なぜそんな形にしたのか?箒とかが置かれている長物コーナーに行く人は年1回の大掃除のときぐらい。これを洗剤コーナーに置けるように開発し、常日頃掃除をしたいというモチベーションに合わせた結果、売り上げ増につながった。要するに「掃除をする」というコトのデザインを考えたから。お客様の感情を追いかけ、それに即した色や形、大きさを考えていくのがデザイン。
芦谷:例えば、花王のクイックルワイパーというモップは3つのパーツに分かれている。なぜそんな形にしたのか?箒とかが置かれている長物コーナーに行く人は年1回の大掃除のときぐらい。これを洗剤コーナーに置けるように開発し、常日頃掃除をしたいというモチベーションに合わせた結果、売り上げ増につながった。要するに「掃除をする」というコトのデザインを考えたから。お客様の感情を追いかけ、それに即した色や形、大きさを考えていくのがデザイン。中島:その部分は私の体験ではマーケティングではと思う?お客様にどう届けるか?どう使ってもらうか?デザインと考え方は似ていて融合されているのでは?
中村:マーケティングは考えの部分だと思う。それを形に落とし込むところがデザイン。でもどちらにしても表層的に捉えてはいけないということ。
中島:中小企業のマーケティングの捉え方について。
 高崎:マーケティングの捉え方で今の話は奥深いもの。中小企業はベタなデザインすらできていないところが多い。技術力は素晴らしいが機能的価値が優先され、情緒的価値、感性的価値には注力してこなかった。技術力だけでデザインは後回しなのが売れなかった原因。
高崎:マーケティングの捉え方で今の話は奥深いもの。中小企業はベタなデザインすらできていないところが多い。技術力は素晴らしいが機能的価値が優先され、情緒的価値、感性的価値には注力してこなかった。技術力だけでデザインは後回しなのが売れなかった原因。中島:人が使うときに“気持ちいいな”という感覚が感性的価値。機能とデザインが融合している。
その感覚をいかに捉えるか?やはり使ってる現場、作ってる現場だと思う。
芦谷:いい事例がある。株式会社青芳製作所は新潟県の金属食器メーカー。障がい者向けスプーンの開発で、最初は技術者(健常者)が考えて作ったがニーズに合わなくて売れない。自分たちの発想の限界を感じ、障がい者に実際に聞きにいって、デザイナーとコラボしながら改良することで使いやすいものができ、高齢者市場でも売れ出した。
中島:強みを活かしつつモノづくりを進めるには“試作ありき”よりまず考えること。ターゲットの特性や状況など、作り手が分からない発見(気づき)などをどう見つけていくか。
コアテクノロジーと現場主義、市場との融合は?
高崎:一番難しいのはマーケティング。うちではお客様カードなどユーザーの意見を開発に反映させている。だが、考える部分では大企業も中小企業も対等。スタートラインは同じだと思う。スケールは違うが…。
中島:つまり情報は外にある。それを自社の技術と結びつける。
そこで新たなものを生み出すポイントは?
 中村:日本の中小企業は自社のコアテクノロジーについて何が強いのか分かってない。よく「何でもできます」と言うが、それでは安心して仕事は出せない。例えば、自動車関係の切削をやっていた企業のSWOT分析を行った結果、医療関係の精密切削に強いことが分かった。そこで兵庫県の医療クラスターとつないだ。今は医療器具づくりを行っている。さらにその企業の強み、実は、切削ではなく様々な金属の削り方“チップの切削データ”を蓄積していたことが強みだった。
中村:日本の中小企業は自社のコアテクノロジーについて何が強いのか分かってない。よく「何でもできます」と言うが、それでは安心して仕事は出せない。例えば、自動車関係の切削をやっていた企業のSWOT分析を行った結果、医療関係の精密切削に強いことが分かった。そこで兵庫県の医療クラスターとつないだ。今は医療器具づくりを行っている。さらにその企業の強み、実は、切削ではなく様々な金属の削り方“チップの切削データ”を蓄積していたことが強みだった。中島:コアテクノロジーを見つけるには外部の目で客観的な評価が必要ということ。
何か一つのことに特化すると消費者が食いついてくるのはマーケティングも同じことではないか。
ここで話を特許に移す。パテントは宝の山?特許を読み漁ることで、少しもじってやると自社のコアテクノロジーとつながるのでは?
 下出:おっしゃるように特許は取得するだけが目的ではない。同業他者の技術分析をすると課題と解決方法が書かれている。技術を整理することで特許マップをつくることができる。特許の戦略的活用も一種のマーケティング。
下出:おっしゃるように特許は取得するだけが目的ではない。同業他者の技術分析をすると課題と解決方法が書かれている。技術を整理することで特許マップをつくることができる。特許の戦略的活用も一種のマーケティング。 中島:いかにオープンな情報を収集して整理していくか。
しかし情報収集には金がかかる?効率的に利用するには?
下出:公的な情報を引き出すこと。特許庁の特許電子図書館(IPDL)を活用する。自社技術関連のインデックスを定期的にウォッチすること。特許出願技術動向調査報告(毎年8分野を中心に)も有効。業界の核となる特許を知ることができる。
中村:コアテクノロジーを見つけるにはSWOT分析を使う。異業種とか飲み友達で集まって客観的に強み、弱み、脅威、機会を発表して意見交換する。弱みと思っていたことが強みである場合も多い。
実は従業員が一番よく知ってたりする。ブレストしながら紙に書いていくと同じキーワードが重なってくる。行政のセミナー利用するのも手。また、大学をうまく使う。ポイントは経営系の教授に直接あたること。
中島:私からのお薦めは、類似技術や商品についてのポジショニングマップ。高い←→安いなど軸を作って4象限で自社の商品のポジションを見える化する。
パテントは言語が難しいし士(さむらい)業は敷居が高い。専門家をうまく使って行く方法は?
 高崎:弁理士とはそもそもコミュニケーションが難しい。我々、医者の話は自分の身体のことだからわかる。弁護士も同様。民法は常識の範囲。
高崎:弁理士とはそもそもコミュニケーションが難しい。我々、医者の話は自分の身体のことだからわかる。弁護士も同様。民法は常識の範囲。特許は馴染みのない言葉が多く専門的。金食い虫で、つぎ込むとなんぼでもお金がかかる。経営者は理解できないことに金を出せない。
自分で知財の勉強をしたり、知的財産管理技能者検定を受けるとかして自分でギャップを埋めること。
逆に経営者は、デザイナーとはレベルが同じと誤解しているのがトラブルの元。
下出:知財教育は特許庁(や近畿経済産業局)が各都道府県で開催する知的財産入門セミナーや実務者向けの研修がある。また市販のeラーニングやDVDといった教材もある。
中島:ここらで狭義のデザインに入る。キーワードは「共感」「使い勝手」どうすればいいか?
 岩田:我が社では顧客の5大プロセスを指標としている。「お客様に知ってもらう」「手に取ってもらう」「買ってもらう」「使ってもらう」「評価してもらう」。例えば商品クレームの蓄積は次の商品の開発材料。「評価=共感」ではないか。他に店舗でお客さんの買い物行動を眺めるというのも勉強になる。
岩田:我が社では顧客の5大プロセスを指標としている。「お客様に知ってもらう」「手に取ってもらう」「買ってもらう」「使ってもらう」「評価してもらう」。例えば商品クレームの蓄積は次の商品の開発材料。「評価=共感」ではないか。他に店舗でお客さんの買い物行動を眺めるというのも勉強になる。中島:コトをデザインするには。ユーザーが使ってみての評価はどうか。
芦谷:ヨーロッパの高級車は扉を閉めると重厚な音がする。匂いも高級車と感じる。五感を戦略的に使っている。
買い手がどう感じるか?突き詰める。イタリアのアレッシーには機能的品質と感情的品質があるという。
中島:感性品質を高めるには?日常でできることはないか。
芦谷:例えば、男同士の会話に女性が入ると合理性とは違った価値観が現れる。特に匂いに対する感じ方などは顕著。女性が考える快適さとかコミュニケーションに着目すると面白い。
岩田:遊びを取り入れること。映画や絵画鑑賞、全然関係なさそうだが「ヒント」は得られる。アクティブに行動することが大事。
中島:感性品質は「らしさ」のようなもの。自分らしさとか我が社らしさ。俯瞰して鳥の目で見ること。サントリーの伊右衛門茶は五感を重視し、日本人がほっとしたときに飲むものという五感マーケティングでの打ち出しを行った。
無機質なデザインに人間らしさを付加して人とモノとの距離感を縮める所作。
 「ターゲット」と「便益」はP&Gが打ち出したマーケティングフレームワーク。誰にWho? 何をWhat? メリットとは少し違うありがたみ。コンセプトを言葉に表してみること。端的に文章化し、顧客に有益であるかどうかという段階で評価する。紙ベースでの評価は金額も時間も短縮できる。
「ターゲット」と「便益」はP&Gが打ち出したマーケティングフレームワーク。誰にWho? 何をWhat? メリットとは少し違うありがたみ。コンセプトを言葉に表してみること。端的に文章化し、顧客に有益であるかどうかという段階で評価する。紙ベースでの評価は金額も時間も短縮できる。中島:最後にプロモーションに入る。
最終製品じゃなくてもプロモーションは必要。自からが持っているものを人に伝える。理解してもらうには?
中村:プロモーションでは強みの押し出し方を考えること。東大阪で100円のネジがドイツで1500円で売れる。強みをしっかり理解するだけで売り方は見えてくる。
中島:ホームページでの強みの見せ方はどうか?日本では総花的なHPが多いように感じるが。
芦谷:ホームページ作りのプロセスが強みを発見することに役立つ。ホームページは漠然と人が入ってくる媒体。まずは情報を大量に詰め込むこと。ブログ(日記)はかたっぱしから情報を入れて行くのに有効なツール。その後で、Googleのアナリティックスなどのアクセス解析でどのページが見られているのか。上位のキーワードを分析すると強みの発見につなげられる。
 中島:最後にまとめ。
中島:最後にまとめ。基本は試作の前に意見を集約すること。本当にそれが必要なのか何度も考えて。
次に外部の専門家を積極的に使って欲しい。最初の1回目は安いから相談だけでもいい。心配なら公的な機関からつないでもらうことも。外部の知識はM&Aと同じ。外部のリソースを買うのは時間とお金の節約。
これから30%人口減社会に突入する。必然的に市場が狭まる。益々、知恵の結集が必要になってくると思う。
皆様ありがとうございました。以上で座談会を終わります。