リゲッタ ドライビングローファー
【TOPICS】ネットショップ初心者向けBASEデザインテーマ「スターターパック」販売開始
「BRIDAL-STYLE」は、2005年に開始し現在まで、結婚準備やウエディングのための情報を提供してきたウェディング情報ポータルサイトです。

結婚式場をお探しの方にむけて、結婚準備に役立つコラムなど、20代から30代のカップルが結婚式を成功させるために必要な情報を網羅しています。また、会員登録や有料コンテンツは一切なく、誰もがどのページでも無料で閲覧できます。
コロナに影響が随分と薄れて、結婚式を控えていたカップルもコロナ前と同様に結婚式を執り行おうとする流れで出てきています。そういった流れを受けて、これから結婚式を行おうと考えているカップルに向けて、式場探しやフェア予約、結婚準備に役立つコラムと、業界全体のトレンドニュースを掲載しています。
【TOPICS】ネットショップ初心者向けBASEデザインテーマ「スターターパック」販売開始
ホームページへの攻撃やハッキングが日々発生している中で、あなたのホームページのセキュリティ対策は万全ですか?
どこか遠い国で起こっていることと思っていませんか?

【TOPICS】ネットショップ初心者向けBASEデザインテーマ「スターターパック」販売開始
2020年8月から0円webコンサルティングサービスを開始いたしました。
コンサルティング費用も、交通費も一切かからず、完全に無料で3回までご利用いただけるwebコンサルティングサービスです!
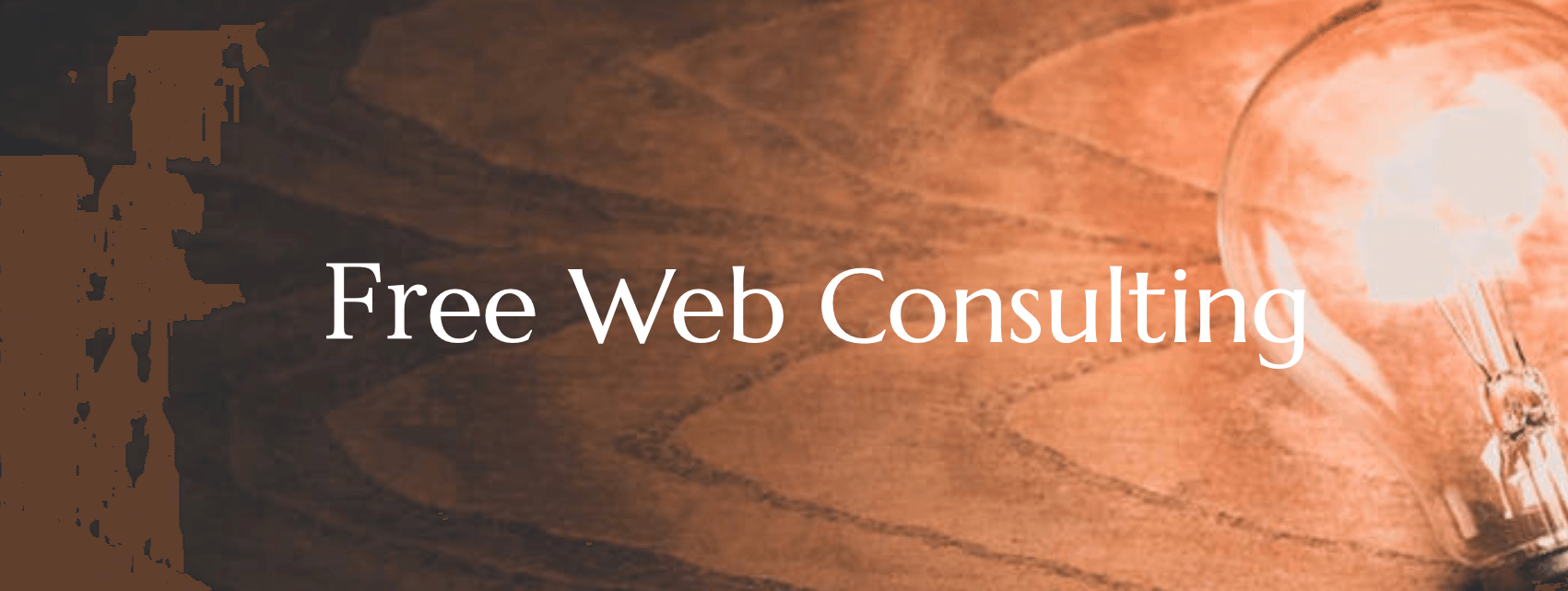
【TOPICS】ネットショップ初心者向けBASEデザインテーマ「スターターパック」販売開始
結婚式場に特化したweb集客コンサルティングに力を入れています。
式場公式サイトのリニューアルから定期的な更新(コンテンツ追加・改善)、ブログマーケティング、SNSアカウントの運用、web広告の運用代行とあらゆる手段を駆使して、式場様個々の体制にあった集客方法をご提案し、実践しています。
【TOPICS】ネットショップ初心者向けBASEデザインテーマ「スターターパック」販売開始

ロゴ・名刺・ホームページの制作実績のご紹介です。
【TOPICS】ネットショップ初心者向けBASEデザインテーマ「スターターパック」販売開始
精密機器のパーツ等、極小サイズの部品や、実際に使用されている商品の外見から見えない位置にある部品、さらには高速駆動しているため通常のビデオカメラでは追い切れないなど、いかに優れた性能を持っていても、機能やアピールポイントが理解されづらい製品・部品は数多く存在します。
【TOPICS】ネットショップ初心者向けBASEデザインテーマ「スターターパック」販売開始
現在、弊社で実施中の光ファイバー初期費用0円キャンペーンについて、先の記事( BROAD-GATE02の初期費用無料キャンペーン再始動!、BROAD-GATE02の0円キャンペーンの解説 )でご説明してきましたが、実際に他の光ファイバーサービスから乗り換えた場合、月額利用料がどうなるのか、表にしてみました。
【TOPICS】ネットショップ初心者向けBASEデザインテーマ「スターターパック」販売開始
光ファイバーBROAD-GATE02の初期費用が無料!とキャンペーンを打ちまして、文字情報だけでお知らせしていますが、いまひとつわかりにくいかと思いますので、キャンペーンページに掲載されている通常お申し込みの場合を元にした解説図をアップします。
【TOPICS】ネットショップ初心者向けBASEデザインテーマ「スターターパック」販売開始
前回、2月〜4月に実施していた光ファイバー BROAD-GATE02の初期費用無料キャンペーンが再度始動します!
今回お申し込みの方も、お申し込み時に必要な初期費用、事務手数料、工事費が無料になります!
是非、この機会をご利用ください。
UCOMオフィシャルパートナーである有限会社流楽の独自キャンペーンです!

【TOPICS】ネットショップ初心者向けBASEデザインテーマ「スターターパック」販売開始
今日からBMB企画展が開催されます。
弊社も出展させて頂くことになりましたので、本日搬入に行ってきました。
※「Tweets by xxxxx_PR」と表示される場合はTwitterが10秒ほど遅延している可能性があります。表示までしばらく待ってみてください。「通知はまだ届いていません」と表示される場合はtwitterの公開設定が不十分な可能性があります。
Webコンサルタントの松崎です。
以前にこのブログでご紹介した「資格スクールを探す」ユーザー視点で見るWeb集客のポイントで、合格率の表示方法や、総額費用の不明確さについて書きました。
今回は、資格スクールを探すユーザーの「資格の種類」に焦点を当てて、それぞれのニーズにどう応えるコンテンツを作ればいいのか、具体的に考えていきます。
資格スクールを選ぶとき、一番大事なのが「どんな資格を目指すか」です。
ビジネス系と法律系では、求める指導内容が全然違います。
医療・福祉系とIT系でも、学習スタイルや期待する効果が変わります。
でも、多くの資格スクールサイトって、対応資格を並べてるだけ。
具体的にその資格でどんな指導を受けられるのかわからないんです。
「この資格なら、ここが最適」って思わせるコンテンツを作ることが、資格スクールのWeb集客の鍵です。
それぞれの資格で、ユーザーがどんなニーズを持っているのか、整理してみましょう。
ユーザーのニーズ
ビジネス系資格を目指す人は、実用性を重視します。
今の仕事に活かせる、転職で評価される。
資格取得が直接キャリアにつながる。
こういう実践的スキル習得のニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
資格取得のメリットを具体的に。
「簿記2級で経理職への転職が有利に」。
「中小企業診断士で独立開業も可能」。
「年収アップ平均〇〇万円」。
キャリアにどう役立つか、明確に示す。
働きながらの学習プランも。
「週2回の夜間コース」。
「土日集中コース」。
「オンライン受講で通勤時間も学習」。
仕事との両立ができることを伝える。
実務直結の内容も強調。
「実務経験豊富な講師陣」。
「実際の業務を想定した演習」。
「合格後すぐに使える知識」。
単なる試験対策じゃないことを示す。
コンテンツの見せ方
「ビジネス系資格」専用ページを作る。
資格別の詳細、学習プラン、キャリアメリット、合格実績。
ビジネス系に必要な情報を集約。
受講生のキャリアチェンジ事例も。
「簿記2級取得で経理職に転職成功」。
「診断士資格でコンサルタントに」。
実際のキャリアアップ例を紹介。
費用対効果も明示。
「受講料〇〇万円」。
「資格取得後の年収アップ平均〇〇万円」。
「投資回収期間:約〇年」。
経済的メリットを数字で示す。
ユーザーのニーズ
法律系資格を目指す人は、将来性を重視します。
独立開業できる、専門性が高い。
人生を変える大きな決断として臨んでる。
こういう独立志向のニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
初学者向けの配慮を明確に。
「法律知識ゼロから合格者多数」。
「基礎の基礎から丁寧に指導」。
「法律用語も分かりやすく説明」。
未経験でも大丈夫なことを伝える。
合格までの標準期間も。
「宅建:6ヶ月の学習で合格」。
「行政書士:1年間の集中学習」。
「司法書士:2〜3年の計画的学習」。
現実的な学習期間を示す。
開業支援の内容も詳しく。
「開業準備セミナー」。
「営業ノウハウ講座」。
「先輩開業者との交流会」。
「開業後の相談サポート」。
合格後のキャリアまで支援することを示す。
コンテンツの見せ方
「法律系資格」専用ページを作る。
資格別詳細、初学者サポート、開業支援、合格者の声。
法律系に必要な情報をまとめる。
開業成功事例も充実。
「行政書士として独立3年目で年収〇〇万円」。
「どんな営業をしたか」「苦労した点」。
リアルな開業ストーリーを紹介。
難易度別の説明も。
「宅建:入門レベル、約6ヶ月」。
「行政書士:中級レベル、約1年」。
「司法書士:最難関レベル、2〜3年」。
段階的にステップアップできることを示す。
ユーザーのニーズ
医療・福祉系資格を目指す人は、社会貢献を重視します。
人の役に立ちたい、安定した職に就きたい。
手に職をつけて、長く働きたい。
こういう安定志向のニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
就職率と就職先を具体的に。
「就職率98%」。
「主な就職先:病院、介護施設、クリニック」。
「資格取得後の平均月給〇〇万円」。
就職の見通しを明確に示す。
実習・実技の充実度も。
「提携施設での実習あり」。
「実技演習で実践力を養成」。
「現場経験豊富な講師が指導」。
実践的に学べることを伝える。
年齢層の幅広さもアピール。
「20代〜60代まで幅広く在籍」。
「未経験からのキャリアチェンジ歓迎」。
「子育て後の再就職に最適」。
誰でも目指せることを示す。
コンテンツの見せ方
「医療・福祉系資格」専用ページを作る。
資格別詳細、実習内容、就職サポート、就職実績。
医療・福祉系に必要な情報を集約。
卒業生の就職事例も。
「40代未経験から介護福祉士に」。
「どんな施設で働いているか」。
「やりがいと苦労」。
実際の就職後の様子を紹介。
給付金対応も明記。
「教育訓練給付金対象講座」。
「実質負担〇〇万円で受講可能」。
経済的な支援制度を活用できることを伝える。
ユーザーのニーズ
IT系資格を目指す人は、将来性と柔軟性を重視します。
需要の高い業界、在宅勤務も可能。
これからの時代に必要なスキル。
こういう将来志向のニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
IT業界の需要を示す。
「IT人材不足で求人倍率〇倍」。
「未経験からIT転職成功者多数」。
「平均年収〇〇万円の成長業界」。
業界の魅力を数字で示す。
実務重視のカリキュラムも。
「実際の開発環境で学習」。
「ポートフォリオ制作サポート」。
「現役エンジニアが講師」。
実践的に学べることを強調。
オンライン学習の充実度も。
「完全オンライン受講可能」。
「質問チャットで即回答」。
「録画視聴で復習し放題」。
場所を選ばず学べることを伝える。
コンテンツの見せ方
「IT系資格」専用ページを作る。
資格別詳細、カリキュラム、就職・副業サポート、受講スタイル。
IT系に必要な情報をまとめる。
転職・副業成功事例も。
「未経験からWebエンジニアに転職」。
「副業で月〇〇万円稼ぐ」。
「フリーランスとして独立」。
多様な働き方の実例を紹介。
最新技術への対応も。
「最新のフレームワークに対応」。
「AI・機械学習講座あり」。
「クラウド技術も学べる」。
時代に合った内容であることを示す。
多くの資格スクールサイトって、対応資格を並べてるだけ。
でも、それじゃあそれぞれの資格でどんな指導を受けられるのかわからない。
ビジネス系を目指す人には、実務直結と費用対効果を。
法律系を目指す人には、開業支援と初学者サポートを。
医療・福祉系を目指す人には、就職率と実習内容を。
IT系を目指す人には、実務スキルとオンライン充実度を。
それなのに、どのページも「合格実績」と「受講料」が載ってるだけ。
どの資格に向いてるのか、どんなキャリアが開けるのか、わからない。
受講生は、「自分が目指す資格」での指導実績が知りたいんです。
ビジネス系を探してる人に、法律系の開業の話をしても響かない。
法律系を目指す人に、就職率の高さばかり強調しても違う。
医療・福祉系を考える人に、最新技術の話をしても関係ない。
それぞれの資格に応じた情報提供ができないと、選ばれません。
受講生のニーズを理解して、その資格で大切なことを、わかりやすく伝える。
これができて初めて、選ばれる資格スクールになるんです。
資格スクールを探してるユーザーは、それぞれ違う資格を目指してます。
その資格に合った情報を、わかりやすく提供できるスクールが選ばれます。
それぞれの資格に必要なコンテンツを、専用ページで丁寧に説明する。
これができれば、「この資格ならここ」って選んでもらえます。
当社が提案している受講生の将来に寄り添うようにサイトを最適化していくWeb集客メソッド「サイトスタイリング™」で、資格の種類ごとに受講生が求める情報を徹底的に分析して、それぞれに応えるコンテンツ設計を行っています。
資格スクールなら、ビジネス系、法律系、医療・福祉系、IT系、それぞれの資格で受講生が何を重視するのかを洗い出し、その情報を整理していきます。キャリアメリットは具体的に、実績は数字で、サポートは詳しく丁寧に、事例はリアルに。それぞれのコンテンツを、受講生が必要とする形で提供するんです。
資格取得は、人生を変える大きな決断。
だからこそ、失敗したくないんです。
「ここなら合格できて、その先のキャリアも開ける」って思ってもらえれば、受講につながります。
そのための第一歩が、資格種類別の情報をしっかり伝えること。
受講生の期待に応える丁寧な情報提供が、選ばれる資格スクールを作り上げます。
資格スクールを選ぶとき、資格の種類で求める情報は大きく変わります。
ビジネス系、法律系、医療・福祉系、IT系。
それぞれの資格で必要な情報を、わかりやすく提供することが大切です。
キャリアメリット、開業支援、就職率、実務スキル。
こういった要素を、専用ページ、事例紹介、実績データ、サポート内容など、適切な形で見せていく。
そうすれば、「ここで学びたい」って思ってもらえます。
あなたのスクールのサイトは、それぞれの資格に応えられていますか?
資格スクールを探している人が本当に知りたい情報がありますか?
一度、それぞれの資格を想定して、じっくり見直してみてください。
きっと、改善できるポイントが見つかるはずです。
初回相談は無料です。
いつでもお気軽にお問い合わせください。
(この記事には画像があります。画像部分は外部ブログサイトで見れます。)
Webコンサルタントの松崎です。
以前に投稿した「学習塾・予備校を探す」ユーザー視点で見るWeb集客のポイントで、合格実績の見せ方や、料金の不透明さについて書きました。
今回は、学習塾・予備校を探すユーザーの「学年・受験段階」に焦点を当てて、それぞれのニーズにどう応えるコンテンツを作ればいいのか、具体的に考えていきます。
学習塾を選ぶとき、一番大事なのが「どの学年・受験段階か」です。
小学生と中学生では、見るポイントが全然違います。
受験学年と非受験学年でも、求める内容や緊急度が変わります。
でも、多くの塾サイトって、コース紹介が載ってるだけ。
具体的にその学年・段階でどんな指導を受けられるのかわからないんです。
「この学年・段階なら、ここが最適」って思わせるコンテンツを作ることが、学習塾のWeb集客の鍵です。
それぞれの学年・段階で、親がどんなニーズを持っているのか、整理してみましょう。
ユーザーのニーズ
低中学年の親は、まず学習習慣を重視します。
机に向かう習慣、宿題をやる習慣。
勉強嫌いにならないように、楽しく学んでほしい。
こういう基礎形成のニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
低学年向けの指導方針を明確に。
「褒めて伸ばす指導」。
「ゲーム感覚で楽しく学習」。
「集中力が続く30分授業」。
無理なく続けられることを伝える。
学習習慣づくりの工夫も。
「宿題の量は無理のない範囲」。
「家庭学習の進め方をアドバイス」。
「保護者へのフィードバック週1回」。
家庭との連携を示す。
教室の雰囲気も大切に。
「明るく楽しい教室」。
「優しい先生たち」。
「お友達と一緒に頑張れる」。
写真で安心できる環境を見せる。
コンテンツの見せ方
「小学生低中学年コース」専用ページを作る。
指導方針、授業の流れ、教室の雰囲気、保護者サポート。
低中学年に必要な情報を集約。
授業の様子を動画で。
「楽しそうに学ぶ子供たち」。
「先生の優しい指導」。
雰囲気が伝わる動画を。
保護者の声も効果的。
「勉強嫌いだった子が、塾に行くのを楽しみにしてます」。
「宿題を自分からやるようになった」。
変化が伝わる声を紹介。
ユーザーのニーズ
中学受験を検討する親は、情報収集を重視します。
受験させるべきか、どの学校を目指すか。
親も子も初めての経験で、不安だらけ。
こういう受験準備のニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
中学受験コースの詳細を。
「4年生2月開講(新5年生)」。
「志望校別クラス編成」。
「主要4科目対応」「難関校対策あり」。
いつから何をするか、明確に。
合格実績も詳しく。
「〇〇中学 5名合格」。
「合格率:受験者の80%」。
「入塾時の偏差値から平均15アップ」。
実績の中身を示す。
受験相談会の案内も。
「中学受験個別相談会(随時開催)」。
「志望校選びのアドバイス」。
「受験スケジュールの立て方」。
受験の不安に寄り添う姿勢を。
コンテンツの見せ方
「中学受験コース」専用ページを作る。
コース詳細、合格実績、カリキュラム、相談会。
中学受験に必要な情報をまとめる。
合格者インタビューも。
「〇〇中学に合格した先輩の声」。
「どんな勉強をしたか」「塾のサポート」。
リアルな体験談が、参考になります。
受験までのロードマップも。
「4年生:基礎固め」。
「5年生:応用力養成」。
「6年生:志望校対策・過去問演習」。
全体像が見えると、計画が立てやすいです。
ユーザーのニーズ
中学生の親は、内申と入試のバランスを重視します。
定期テストも大事、実力も必要。
部活も頑張りたいけど、受験も心配。
こういう両立サポートのニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
中学生コースの特徴を。
「定期テスト対策あり(2週間前から)」。
「内申点アップのサポート」。
「部活との両立を応援」。
中学生特有のニーズに対応してることを示す。
学年別のポイントも。
「中1・中2:基礎固めと学習習慣」。
「中3:受験対策本格化(9月〜)」。
「入試直前:過去問演習・面接対策」。
学年ごとの重点を明確に。
合格実績と内申アップ実績も。
「〇〇高校 10名合格」。
「内申点平均3ポイントアップ」。
「定期テスト平均20点アップ」。
数字で成果を示す。
コンテンツの見せ方
「中学生・高校受験コース」専用ページを作る。
定期テスト対策、受験対策、合格実績、時間割。
中学生に必要な情報を集約。
部活との両立事例も。
「野球部と塾を両立して志望校合格」。
「どんなスケジュールで勉強したか」。
両立できることを具体例で示す。
授業の振替制度も明記。
「部活の大会で休んでも振替OK」。
「体調不良時はオンライン授業」。
柔軟に対応できることを伝える。
ユーザーのニーズ
高校生は、自分の意思で塾を選びます。
親の意見も参考にするけど、最終的には本人の判断。
だから、本人に響く情報が必要。
こういう自主的学習のニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
大学受験コースの詳細を。
「国公立大対策」「私立大対策」。
「推薦・総合型選抜対策」。
「医学部・難関大コース」。
志望校別の対応を明確に。
合格実績も大学名で。
「〇〇大学 3名合格」。
「国公立大合格率60%」。
「早慶上智 5名合格」。
どのレベルの大学に合格してるか示す。
学習環境も重要。
「自習室完備(朝7時〜夜10時)」。
「質問対応いつでもOK」。
「参考書・赤本貸出あり」。
自習しやすい環境を伝える。
コンテンツの見せ方
「高校生・大学受験コース」専用ページを作る。
コース詳細、合格実績、自習環境、講師陣。
大学受験に必要な情報をまとめる。
合格体験記も充実。
「現役で〇〇大学に合格した先輩の話」。
「どんな勉強法で合格したか」。
「塾をどう活用したか」。
先輩の声が、モチベーションに。
オンライン・映像授業の説明も。
「有名講師の映像授業見放題」。
「対面授業との組み合わせ可能」。
「自分のペースで学習できる」。
選択肢があることを示す。
多くの学習塾サイトって、コース紹介が載ってるだけ。
でも、それじゃあそれぞれの学年・段階でどんな指導を受けられるのかわからない。
低中学年の親には、学習習慣づくりと楽しさを。
中学受験を考える親には、合格実績と受験サポートを。
中学生の親には、定期テスト対策と部活両立を。
高校生には、志望大学別対策と自習環境を。
それなのに、どのページも「授業料」と「時間割」が載ってるだけ。
どの学年・段階に向いてるのか、どんな成果が期待できるのか、わからない。
親や生徒は、「自分の学年・段階」に合った塾が欲しいんです。
低学年を探してる親に、受験対策の厳しさを前面に出しても怖がらせるだけ。
中学受験を考える親に、一般的な学習習慣の話では物足りない。
高校生に、親目線の説明ばかりしても響かない。
それぞれの学年・段階に応じた情報提供ができないと、選ばれません。
ユーザーの状況を理解して、その時に必要な指導と情報を、わかりやすく伝える。
これができて初めて、選ばれる学習塾になります。
学習塾を探してるユーザーは、それぞれ違う学年・受験段階にいます。
その段階に合った情報を、わかりやすく提供できる塾が選ばれます。
小学生低中学年→学習習慣、楽しい雰囲気、保護者サポート。
中学受験準備→合格実績、志望校対策、受験相談。
中学生→定期テスト対策、内申アップ、部活両立。
高校生→志望大学別対策、自習環境、合格体験記。
それぞれの学年・段階に必要なコンテンツを、専用ページで丁寧に説明する。
これができれば、「この段階ならここ」って選んでもらえます。
当社が提案している成績向上を願う親子に寄り添ってサイトを最適化するWeb集客メソッド「サイトスタイリング™」で、学年・受験段階ごとに親や生徒が求める情報を徹底的に分析して、それぞれに応えるコンテンツ設計を行っています。
学習塾なら、小学生低中学年、中学受験、中学生、高校生、それぞれの段階で親や生徒が何を重視するのかを洗い出し、その情報を整理していきます。指導方針は明確に、実績は具体的に、環境は写真で魅力的に、体験談はリアルに。それぞれのコンテンツを、ユーザーが必要とする形で提供するんです。
塾選びは、子供の学力と将来に関わる大切な選択。
だからこそ、失敗したくないんです。
「ここなら成績が上がる」って思ってもらえれば、入塾につながります。
そのための第一歩が、学年・段階別の情報をしっかり伝えること。
親や生徒の期待に応える丁寧な情報提供が、選ばれる学習塾を作り上げます。
学習塾・予備校を選ぶとき、学年・受験段階で求める情報は大きく変わります。
小学生低中学年、中学受験準備、中学生、高校生。
それぞれの段階で必要な情報を、わかりやすく提供することが大切です。
指導方針、合格実績、カリキュラム、学習環境。
こういった要素を、専用ページ、動画、合格体験記、実績データなど、適切な形で見せていく。
そうすれば、「ここに通いたい」って思ってもらえます。
あなたの塾のサイトは、それぞれの段階に応えられていますか?
学習塾を探している親や生徒が本当に知りたい情報がありますか?
一度、それぞれの学年・段階を想定して、じっくり見直してみてください。
きっと、改善できるポイントが見つかるはずです。
初回相談は無料です。
いつでもお気軽にお問い合わせください。
(この記事には画像があります。画像部分は外部ブログサイトで見れます。)
Webコンサルタントの松崎です。
以前書いた「子供の習い事を探す」ユーザー視点で見るWeb集客のポイントで、料金体系の複雑さや、体験レッスンの申込みハードルについて書きました。
今回は、子供の習い事を探す親の「習い事の種類」に焦点を当てて、それぞれのニーズにどう応えるコンテンツを作ればいいのか、具体的に考えていきます。
子供の習い事を選ぶとき、一番大事なのが「どんな種類の習い事か」です。
スポーツ系と芸術系では、親が見るポイントが全然違います。
学習系と伝統文化系でも、期待する効果や優先順位が変わります。
でも、多くの習い事教室のサイトって、コース紹介が載ってるだけ。
具体的にその種類の習い事で子供がどう成長するのかわからないんです。
「この種類なら、ここが最適」って思わせるコンテンツを作ることが、習い事教室のWeb集客の鍵です。
それぞれの種類で、親がどんなニーズを持っているのか、整理してみましょう。
ユーザーのニーズ
スポーツ系を選ぶ親は、健康と運動能力を重視します。
体が弱い子を強くしたい、運動が苦手な子を好きにさせたい。
体を動かす楽しさを知ってほしい。
こういう身体的成長のニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
年齢・レベル別のクラス編成を明確に。
「幼児クラス(3〜6歳):水慣れ中心」。
「小学生初級(1〜3年):基礎技術習得」。
「小学生中級・上級:競技志向」。
どのクラスが合うか、わかりやすく。
指導内容と目標も具体的に。
「年間カリキュラム」。
「3ヶ月でクロール25m目標」。
「半年で逆上がりができるように」。
成長の道筋が見えると、期待が持てます。
安全対策も詳しく。
「指導員全員が救命講習受講済み」。
「AED設置」「怪我の対応マニュアル」。
「保険加入」。
安心して任せられることを伝える。
コンテンツの見せ方
「スポーツ系習い事」専用ページを作る。
クラス編成、年間カリキュラム、指導方針、安全対策。
スポーツ系に必要な情報を集約。
実際のレッスン動画も。
「幼児クラスの楽しい雰囲気」。
「上級クラスの真剣な練習」。
動画で指導の様子が見えると、イメージしやすいです。
保護者の声も効果的。
「運動嫌いだった子が、今では毎週楽しみに」。
「体力がついて、風邪をひきにくくなった」。
実際の変化が伝わると、期待が持てます。
ユーザーのニーズ
芸術系を選ぶ親は、感性と表現力を重視します。
音楽や絵画を楽しんでほしい、創造性を伸ばしたい。
でも、厳しすぎて嫌いになるのは避けたい。
こういう感性育成のニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
指導方針を詳しく。
「楽しみながら上達」。
「一人ひとりの個性を大切に」。
「褒めて伸ばす指導」。
どんな雰囲気で学べるか、明確に。
発表の機会も具体的に。
「年1回の発表会」。
「コンクール参加も可能(希望者のみ)」。
「作品展示会」「動画発表会」。
成果を披露できる場があることを伝える。
先生の経歴も詳しく。
「音楽大学卒業」「コンクール受賞歴」。
「指導歴〇年」「生徒のコンクール入賞実績」。
専門性と実績を示す。
コンテンツの見せ方
「芸術系習い事」専用ページを作る。
指導方針、発表機会、先生紹介、生徒作品。
芸術系に必要な情報をまとめる。
生徒の作品や演奏も紹介。
「生徒さんの絵画作品ギャラリー」。
「発表会のピアノ演奏動画」。
実際のレベルが見えると、期待値が持てます。
レッスン室の雰囲気も。
「明るく広いレッスン室」。
「グランドピアノ完備」「画材豊富」。
環境が整ってることを写真で伝える。
ユーザーのニーズ
学習系を選ぶ親は、将来性と実用性を重視します。
英語は必須、プログラミングも大事。
でも、詰め込みじゃなくて、楽しく身につけてほしい。
こういう実用的スキル習得のニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
カリキュラムを年齢別に。
「幼児(3〜6歳):遊びながら英語に触れる」。
「小学生低学年:フォニックスと基礎文法」。
「小学生高学年:英検3級レベルを目指す」。
年齢ごとの到達目標を明確に。
実績も具体的に。
「英検合格実績:5級〇名、4級〇名」。
「プログラミングコンテスト入賞」。
「中学受験合格実績」。
数字で成果を示す。
授業の進め方も説明。
「少人数制(定員6名)」。
「個別指導とグループ学習の組み合わせ」。
「オンライン授業も可能」。
学習環境を具体的に。
コンテンツの見せ方
「学習系習い事」専用ページを作る。
カリキュラム、実績、授業スタイル、料金。
学習系に必要な情報を集約。
体験レッスンの様子も。
「実際の授業風景」。
「子供たちの集中した表情」。
雰囲気が伝わる写真や動画を。
保護者の声も重要。
「英語が好きになって、自分から勉強するように」。
「プログラミングで論理的思考が育った」。
学習効果が伝わる声を紹介。
ユーザーのニーズ
伝統文化系を選ぶ親は、人間形成を重視します。
礼儀、集中力、忍耐力。
習い事を通じて、内面を鍛えてほしい。
こういう人格形成のニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
指導方針と教育理念を。
「礼に始まり礼に終わる」。
「挨拶、返事、姿勢を大切に」。
「技術だけでなく、心も育てる」。
伝統文化の価値を明確に伝える。
段級位制度と目標設定も。
「そろばん:10級から段位まで」。
「書道:毛筆・硬筆の級位認定」。
「空手:帯の色で成長が見える」。
目に見える成長があることを示す。
先生の人柄も重視。
「師範の経歴と指導理念」。
「厳しくも温かい指導」。
「子供一人ひとりと向き合う姿勢」。
人として尊敬できる先生であることを。
コンテンツの見せ方
「伝統文化系習い事」専用ページを作る。
指導理念、段級位制度、師範紹介、道場の雰囲気。
伝統文化系に必要な情報をまとめる。
稽古の様子も詳しく。
「正座での挨拶から始まる稽古」。
「真剣に取り組む子供たち」。
礼儀と集中が身につく環境を見せる。
卒業生の声も効果的。
「そろばんで培った集中力が受験に役立った」。
「書道で忍耐強くなった」。
長期的な効果が伝わる声を。
多くの習い事教室サイトって、コース紹介が載ってるだけ。
でも、それじゃあそれぞれの種類でどんな成長が期待できるのかわからない。
スポーツ系を探す親には、体力向上と安全対策を。
芸術系を探す親には、個性尊重と発表機会を。
学習系を探す親には、実績と将来性を。
伝統文化系を探す親には、人格形成と礼儀を。
それなのに、どのページも「月謝」と「時間割」が載ってるだけ。
どんな種類の習い事に向いてるのか、どんな効果があるのか、わからない。
親は、「この種類の習い事」で子供がどう成長するか知りたいんです。
スポーツを探してる親に、芸術の感性の話をしても響かない。
学習系を求める親に、精神修養の話ばかりしても違う。
伝統文化を探す親に、楽しさばかり強調しても物足りない。
それぞれの種類に応じた情報提供ができないと、選ばれません。
親のニーズを理解して、その習い事の種類で大切なことを、わかりやすく伝える。
これができて初めて、選ばれる習い事教室になるんです。
習い事を探してる親は、それぞれ違う種類の習い事を求めてます。
その種類に合った情報を、わかりやすく提供できる教室が選ばれます。
それぞれの種類に必要なコンテンツを、専用ページで丁寧に説明する。
これができれば、「この種類ならここ」って選んでもらえます。
当社が提案している親子のニーズを汲み取ってサイトを最適化するWeb集客メソッド「サイトスタイリング™」では、習い事の種類ごとに親が求める情報を徹底的に分析して、それぞれに応えるコンテンツ設計を行っています。
習い事教室なら、スポーツ系、芸術系、学習系、伝統文化系、それぞれの種類で親が何を重視するのかを洗い出し、その情報を整理していきます。カリキュラムは具体的に、実績は数字で、先生は顔が見えるように、理念は明確に。それぞれのコンテンツを、親が必要とする形で提供するんです。
習い事選びは、子供の将来に関わる大切な選択。
だからこそ、失敗したくないんです。
「ここなら子供が成長できる」って思ってもらえれば、入会につながります。
そのための第一歩が、種類別の情報をしっかり伝えること。
親の期待に応える丁寧な情報提供が、選ばれる習い事教室を作り上げます。
子供の習い事を選ぶとき、習い事の種類で求める情報は大きく変わります。
スポーツ系、芸術系、学習系、伝統文化系。
それぞれの種類で必要な情報を、わかりやすく提供することが大切です。
カリキュラム、指導方針、実績、先生紹介。
こういった要素を、専用ページ、動画、生徒作品、保護者の声など、適切な形で見せていく。
そうすれば、「ここに通わせたい」って思ってもらえます。
あなたの教室のサイトは、それぞれの種類に応えられていますか?
習い事を探している親が本当に知りたい情報がありますか?
一度、それぞれの種類を想定して、じっくり見直してみてください。
きっと、改善できるポイントが見つかるはずです。
初回相談は無料です。
いつでもお気軽にお問い合わせください。
(この記事には画像があります。画像部分は外部ブログサイトで見れます。)
Webコンサルタントの松崎です。
検索行動のシリーズ記事で取り上げた「介護サービスを探す」ユーザー視点で見るWeb集客のポイントで、料金の不透明さや、空き状況がわからない問題について書きました。
今回は、介護サービスを探すユーザーの「サービスの種類」に焦点を当てて、それぞれのニーズにどう応えるコンテンツを作ればいいのか、具体的に考えていきます。
介護サービスを探すとき、一番大事なのが「どんなサービスを求めるか」です。
日中だけ預けたい人と、24時間施設で看てほしい人では、見るポイントが全然違います。
自宅での介護を支えてほしい人と、短期間だけ利用したい人でも、優先順位が変わります。
でも、多くの介護事業者サイトって、提供サービスを並べてるだけ。
具体的にそのサービスでどんな生活になるのかわからないんです。
「このサービスなら、ここが最適」って思わせるコンテンツを作ることが、介護事業者のWeb集客の鍵です。
それぞれのサービスで、ユーザーがどんなニーズを持っているのか、整理してみましょう。
ユーザーのニーズ
デイサービスを探す家族は、在宅介護を続けたいんです。
夜は家で過ごすけど、日中は預かってほしい。
仕事に行く間、安心して任せられる場所が欲しい。
こういう在宅介護支援のニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
一日の流れを詳しく。
「9:00 お迎え」「10:00 健康チェック・入浴」。
「12:00 昼食」「13:00 レクリエーション」。
「15:00 おやつ・機能訓練」「16:00 お送り」。
具体的な過ごし方を時間割で示す。
送迎エリアと時間も明確に。
「送迎対応エリア:〇〇市全域」。
「お迎え時間:8:30〜9:30の間」。
「お送り時間:16:00〜17:00の間」。
送迎の詳細がわかると、利用しやすい。
食事とレクリエーションも。
「管理栄養士による献立」。
「食事形態:普通食、きざみ食、ペースト食」。
「レクリエーション:体操、歌、ゲーム、季節行事」。
写真で楽しそうな雰囲気を伝える。
コンテンツの見せ方
「デイサービス」専用ページを作る。
一日の流れ、送迎エリア、食事・入浴、レクリエーション。
デイサービスに必要な情報を集約。
実際の様子を動画で。
「レクリエーションの様子」。
「楽しく体操する利用者さん」。
動画があると、雰囲気が伝わりやすいです。
利用者家族の声も。
「母が毎日楽しみに通ってます」。
「仕事中も安心して任せられます」。
実際の満足度が伝わると、選びやすいです。
ユーザーのニーズ
訪問介護を探す家族は、住み慣れた家での生活を守りたいんです。
施設には入れたくない、本人も自宅がいいと言ってる。
でも、家族だけでは限界。
こういう在宅支援のニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
サービス内容を具体的に。
「身体介護:食事介助、排泄介助、入浴介助、着替え」。
「生活援助:掃除、洗濯、買い物、調理」。
何をしてくれるか、何ができないか、明確に。
対応時間帯も明記。
「24時間対応可能」。
「早朝(6:00〜8:00)、夜間(18:00〜22:00)」。
「深夜(22:00〜6:00)も対応」。
時間の柔軟性を示す。
ヘルパーの紹介も。
「経験豊富なヘルパーが担当」。
「介護福祉士資格保有者多数」。
「定期的な研修で質を維持」。
顔写真付きで安心感を。
コンテンツの見せ方
「訪問介護」専用ページを作る。
サービス内容、対応時間、料金例、ヘルパー紹介。
訪問介護に必要な情報をまとめる。
利用シーン別の説明も。
「一人暮らしの父のための週3回訪問」。
「老老介護の夫婦のための毎日訪問」。
具体的なケースで利用イメージを。
安心のポイントも伝える。
「担当ヘルパー制で顔なじみに」。
「緊急時の連絡体制」。
「個人情報の厳守」。
信頼関係が築けることを示す。
ユーザーのニーズ
施設入所を検討する家族は、重い決断をしてます。
在宅では限界、でも施設に入れることへの罪悪感。
本人の気持ち、経済的負担、すべてを考えた上での選択。
こういう切実なニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
施設での一日を詳しく。
「6:30 起床」「7:00 朝食」。
「午前中 入浴、機能訓練、レクリエーション」。
「12:00 昼食」「午後 散歩、趣味活動、休息」。
「18:00 夕食」「21:00 就寝」。
どんな生活を送るか、具体的に示す。
料金を明確に。
「月額利用料:15万円(介護度3の場合)」。
「内訳:居住費5万円、食費4万円、介護費6万円」。
「入居一時金:不要(または○○万円)」。
トータルでいくらか、わかりやすく。
医療体制も詳しく。
「看護師24時間配置」。
「協力医療機関:〇〇病院」。
「訪問診療:月2回」。
医療面の安心を伝える。
コンテンツの見せ方
「施設入所」専用ページを作る。
施設の一日、居室タイプ、料金、医療体制、入居の流れ。
施設入所に必要な情報を集約。
居室と共用スペースの写真も。
「個室の様子」「食堂」「浴室」。
「リビング」「庭」。
実際の生活空間が見えると、イメージしやすいです。
入居者・家族の声も。
「最初は罪悪感があったけど、ここに入れて良かった」。
「スタッフが親身で、母も笑顔が増えた」。
入所後の満足度が伝わると、決断しやすいです。
ユーザーのニーズ
ショートステイを探す家族は、一時的な支援が必要なんです。
介護疲れで倒れそう、出張で留守にする。
数日だけでも預かってもらえれば、何とかなる。
こういうレスパイトケアのニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
利用期間と予約方法を明確に。
「1泊2日から利用可能」。
「最長30日まで連続利用可」。
「予約:1ヶ月前から受付」。
「空き状況:お電話でお問い合わせください」。
柔軟に対応できることを伝える。
料金も一泊単位で。
「1泊2日:8,000円(介護度2の場合)」。
「食事代:1,500円/日」。
「その他:日用品持ち込みまたは実費」。
短期利用の料金がわかるように。
持ち物リストも。
「着替え(〇日分)」「内服薬」。
「愛用の寝具(必要な方のみ)」。
「入れ歯洗浄剤」「その他日用品」。
準備がスムーズにできる情報を。
コンテンツの見せ方
「ショートステイ」専用ページを作る。
利用期間、料金、一日の流れ、持ち物リスト。
ショートステイに必要な情報をまとめる。
よくある利用ケースも。
「介護者の休息のために月1回3泊4日」。
「家族旅行の間の5泊6日」。
「退院直後のお試し1泊2日」。
具体的な使い方を示す。
初めての方へのメッセージも。
「初めてのショートステイで不安な方へ」。
「施設の雰囲気に慣れるまでスタッフがサポート」。
「見学・お試し利用も可能です」。
安心して利用できることを伝える。
多くの介護事業者サイトって、提供サービスを並べてるだけ。
デイサービス、訪問介護、施設入所、ショートステイ。
でも、それじゃあそれぞれのサービスでどんな生活になるのかわからない。
デイサービスを探す人には、一日の流れと送迎を。
訪問介護を探す人には、サービス内容と対応時間を。
施設入所を検討する人には、料金と医療体制を。
ショートステイを使いたい人には、予約方法と柔軟性を。
それなのに、どのページも「サービス内容」が載ってるだけ。
どんな人に向いてるのか、どんな生活になるのか、わからない。
ユーザーは、「自分が求めるサービス」の詳しい情報が欲しいんです。
デイサービスを探してる人に、施設入所の長い説明をしても意味がない。
訪問介護を求める人に、通所の話をしても響かない。
ショートステイを使いたい人に、長期入所の料金を見せても不要。
それぞれのサービスに応じた情報提供ができないと、選ばれません。
ユーザーのニーズを理解して、そのサービスで必要な情報を、わかりやすく提供する。
これができて初めて、選ばれる介護事業者になるんです。
介護サービスを探してるユーザーは、それぞれ違うサービスを求めてます。
そのサービスに合った情報を、わかりやすく提供できる事業者が選ばれます。
それぞれのサービスに必要なコンテンツを、専用ページで丁寧に説明する。
これができれば、「このサービスならここ」って選んでもらえます。
当社が提案している利用者家族のニーズに寄り添ってサイトを最適化するWeb集客メソッド「サイトスタイリング™」は、サービスの種類ごとに家族が求める情報を徹底的に分析して、それぞれに応えるコンテンツ設計を行います。
介護事業者なら、デイサービス、訪問介護、施設入所、ショートステイ、それぞれのサービスで家族が何を重視するのかを洗い出し、その情報を整理していきます。一日の流れは時間割で、料金は内訳で明確に、スタッフは顔が見えるように、医療体制は具体的に。それぞれのコンテンツを、家族が必要とする形で提供するんです。
介護サービス選びは、家族にとって重く切実な選択。
だからこそ、失敗したくないんです。
「ここなら安心して任せられる」って思ってもらえれば、利用につながります。
そのための第一歩が、サービス種類別の情報をしっかり伝えること。
家族の不安に寄り添った丁寧な情報提供が、選ばれる介護事業者を作り上げます。
介護サービスを選ぶとき、サービスの種類で求める情報は大きく変わります。
デイサービス、訪問介護、施設入所、ショートステイ。
それぞれのサービスで必要な情報を、わかりやすく提供することが大切です。
一日の流れ、料金内訳、医療体制、予約方法。
こういった要素を、専用ページ、写真、動画、利用者の声など、適切な形で見せていく。
そうすれば、「ここに任せたい」って思ってもらえます。
あなたの事業所のサイトは、それぞれのサービスに応えられていますか?
介護サービスを探している家族が本当に知りたい情報がありますか?
一度、それぞれのサービスを想定して、じっくり見直してみてください。
きっと、改善できるポイントが見つかるはずです。
初回相談は無料です。
いつでもお気軽にお問い合わせください。
(この記事には画像があります。画像部分は外部ブログサイトで見れます。)
Webコンサルタントの松崎です。
少し前に投稿したユーザー視点で集客を見るシリーズ記事「薬局を探す」ユーザー視点で見るWeb集客のポイントを投稿しましたが、そこで営業時間の見つけにくさや、取り扱い医薬品の不明確さについて書きました。
今回は、薬局を探すユーザーの「利用シーン」に焦点を当てて、それぞれのニーズにどう応えるコンテンツを作ればいいのか、具体的に考えていきます。
薬局を利用するとき、一番大事なのが「どんなシーンで利用するか」です。
処方箋を持って急いでる人と、市販薬をじっくり選びたい人では、見るポイントが全然違います。
健康相談したい人と、在宅医療を求める人でも、優先順位が変わります。
でも、多くの薬局サイトって、営業時間とアクセスが載ってるだけ。
具体的にそのシーンでどんなサービスが受けられるのかわからないんです。
「このシーンなら、ここが最適」って思わせるコンテンツを作ることが、薬局のWeb集客の鍵です。
それぞれのシーンで、ユーザーがどんなニーズを持っているのか、整理してみましょう。
ユーザーのニーズ
処方箋を持った人は、急いでます。
病院で診察を受けて、処方箋をもらった。
早く薬を飲みたいから、スムーズに受け取りたい。
こういう緊急性のあるニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
処方箋受付の利便性を強調。
「処方箋事前送信で待ち時間短縮」。
「LINEで簡単送信」「アプリで写真を送るだけ」。
事前送信の方法を図解で説明。
在庫確認サービスも。
「薬の在庫を事前に確認できます」。
「取り寄せが必要な場合は即連絡」。
行ったのに薬がない、という不安を解消。
ジェネリック対応も明記。
「ジェネリック医薬品に変更可能」。
「薬剤師が丁寧に説明します」。
「先発品との違いをわかりやすく」。
選択肢があることを伝える。
コンテンツの見せ方
「処方箋をお持ちの方へ」専用ページを作る。
事前送信方法、待ち時間の目安、ジェネリック対応。
処方箋を持った人に必要な情報を集約。
処方箋送信の手順も詳しく。
「①LINEで友だち追加」。
「②処方箋を撮影して送信」。
「③準備完了の連絡を受け取る」。
「④来局して受け取り」。
ステップ形式でわかりやすく。
受け取り時間の目安も。
「送信から約30分で準備完了」。
「混雑時は1時間程度かかる場合も」。
現実的な時間を示す。
ユーザーのニーズ
市販薬を買いたい人は、すぐに対処したいんです。
頭痛、風邪、腹痛。
今すぐ症状を和らげたいから、営業してる薬局を探してる。
こういう切実なニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
営業時間を目立たせる。
「平日 9:00〜21:00」。
「土日祝 9:00〜19:00」。
「年中無休(年末年始除く)」。
トップページの一番目立つ場所に。
本日の営業状況も。
「本日営業中」「営業時間まであと○時間」。
リアルタイムの情報を提示。
症状別のおすすめ市販薬も。
「頭痛に効く薬」「風邪薬の選び方」。
「胃薬の種類と使い分け」。
薬剤師目線でのアドバイスを掲載。
コンテンツの見せ方
「市販薬をお探しの方へ」専用ページを作る。
営業時間、症状別おすすめ、相談体制、駐車場情報。
市販薬を買いたい人に必要な情報をまとめる。
薬剤師への相談も案内。
「市販薬選びでお困りの方」。
「薬剤師が症状をお聞きして最適な薬をご提案」。
「相談無料、お気軽にどうぞ」。
専門家のサポートがあることを伝える。
夜間・休日対応も強調。
「仕事帰りでも寄れる21時まで営業」。
「土日も営業で安心」。
通いやすさをアピール。
ユーザーのニーズ
かかりつけ薬局を探す人は、長期的な視点で選びます。
薬歴管理、健康相談、飲み合わせチェック。
いつでも相談できる、信頼できる薬局が欲しい。
こういう継続的なニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
かかりつけ薬局のメリットを説明。
「薬歴を一元管理で安心」。
「複数の病院の薬の飲み合わせチェック」。
「健康相談いつでもOK」。
かかりつけの価値を具体的に伝える。
薬剤師の顔を見せる。
「薬剤師の紹介」写真、経歴、得意分野。
「糖尿病の薬に詳しい薬剤師が在籍」。
「小児の服薬指導が得意」。
人柄と専門性を伝える。
健康サポートサービスも。
「血圧測定」「健康相談会」。
「お薬手帳アプリ対応」。
継続的なサポート体制を示す。
コンテンツの見せ方
「かかりつけ薬局」専用ページを作る。
かかりつけのメリット、薬剤師紹介、サービス内容。
長く付き合いたい人に必要な情報を集約。
患者さんの声も効果的。
「いつも丁寧に相談に乗ってくれる」。
「薬の飲み合わせを指摘してくれて助かった」。
信頼関係が伝わる声を紹介。
定期的な情報発信も。
「健康ブログ」「季節の健康情報」。
「薬の正しい飲み方コラム」。
専門性をアピールする。
ユーザーのニーズ
在宅医療を求める人は、具体的な情報が欲しいんです。
高齢の親、寝たきりの家族。
通院が困難だから、自宅に来てほしい。
こういう切実なニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
在宅医療サービスを詳しく説明。
「訪問薬剤指導とは」。
「薬剤師がご自宅を訪問」。
「薬の管理、服薬指導、残薬整理」。
何をしてくれるのか具体的に。
対応エリアと費用も明確に。
「対応エリア:〇〇市、〇〇区」。
「費用:医療保険適用で1回500円程度(1割負担の場合)」。
「交通費なし」。
利用しやすい情報を提示。
利用の流れも説明。
「①医師の指示書が必要」。
「②薬局に連絡・相談」。
「③訪問日時の調整」。
「④定期的に訪問」。
スムーズに利用開始できることを示す。
コンテンツの見せ方
「在宅医療・訪問薬剤指導」専用ページを作る。
サービス内容、対応エリア、費用、利用の流れ。
在宅医療を求める人に必要な情報をまとめる。
実際の訪問事例も。
「寝たきりの母の薬を管理してもらって助かってます」。
「残薬が整理できて無駄がなくなった」。
実際の利用者の声を紹介。
医療機関との連携も。
「病院、ケアマネージャーと連携」。
「チーム医療の一員として」。
総合的なサポート体制を伝える。
多くの薬局サイトって、営業時間とアクセスが載ってるだけ。
でも、それじゃあそれぞれのシーンに合った情報が見つからない。
処方箋を持ってる人には、事前送信と待ち時間を。
市販薬を買いたい人には、営業時間と症状別おすすめを。
かかりつけを探す人には、薬剤師の顔とサポート体制を。
在宅医療を求める人には、サービス内容と費用を。
それなのに、どのページも「取り扱い商品」が載ってるだけ。
どんなシーンの人に向いてるのか、わからない。
ユーザーは、「自分のシーン」に合った薬局が欲しいんです。
処方箋を持って急いでる人に、健康相談の話をしても今じゃない。
市販薬を買いたい人に、かかりつけのメリットを説明しても響かない。
在宅医療を求める人に、一般的な営業時間だけ示しても足りない。
それぞれのシーンに応じた情報提供ができないと、選ばれません。
ユーザーのシーンを理解して、その時に必要な情報を、わかりやすく提供する。
これができて初めて、選ばれる薬局になるんです。
薬局を利用するユーザーは、それぞれ違うシーンで来局します。
そのシーンに合った情報を、わかりやすく提供できる薬局が選ばれます。
それぞれのシーンに必要なコンテンツを、専用ページで丁寧に説明する。
これができれば、「このシーンならここ」って選んでもらえます。
当社が提案している患者さんの目線でホームページ最適化を行うWeb集客メソッド「サイトスタイリング™」で、利用シーンごとに患者さんが求める情報を徹底的に分析して、それぞれに応えるコンテンツ設計を行っています。
薬局なら、処方箋、市販薬、かかりつけ、在宅医療、それぞれのシーンで患者さんが何を重視するのかを洗い出し、その情報を整理していきます。事前送信は手順をわかりやすく、営業時間は目立つ場所に、薬剤師は顔が見えるように、費用は明確に。それぞれのコンテンツを、患者さんが必要とする形で提供するんです。
薬局選びは、健康に関わる大切な選択。
だからこそ、失敗したくないんです。
「ここなら自分のシーンに対応してくれる」って思ってもらえれば、来局につながります。
そのための第一歩が、シーン別の情報をしっかり伝えること。
患者さんのシーンに寄り添った丁寧な情報提供が、選ばれる薬局を作り上げます。
薬局を選ぶとき、利用シーンで求める情報は大きく変わります。
処方箋を持って、市販薬購入、かかりつけ、在宅医療。
それぞれのシーンで必要な情報を、わかりやすく提供することが大切です。
事前送信方法、営業時間、薬剤師紹介、サービス内容。
こういった要素を、専用ページ、手順説明、利用者の声など、適切な形で見せていく。
そうすれば、「ここに行きたい」って思ってもらえます。
あなたの薬局のサイトは、それぞれのシーンに応えられていますか?
薬局を探している人が本当に知りたい情報がありますか?
一度、それぞれのシーンを想定して、じっくり見直してみてください。
きっと、改善できるポイントが見つかるはずです。
初回相談は無料です。
いつでもお気軽にお問い合わせください。
(この記事には画像があります。画像部分は外部ブログサイトで見れます。)
Webコンサルタントの松崎です。
以前のこのシリーズで投稿した「整体・マッサージを探す」ユーザー視点で見るWeb集客のポイントで、料金体系の複雑さや、施術内容の曖昧さについて書きました。
今回は、整体・マッサージを探すユーザーの「来店目的」に焦点を当てて、それぞれのニーズにどう応えるコンテンツを作ればいいのか、具体的に考えていきます。
整体・マッサージを探すとき、一番大事なのが「どんな目的で行くか」です。
痛みを治したい人と、リラックスしたい人では、見るポイントが全然違います。
美容目的の人と、スポーツのパフォーマンスを上げたい人でも、優先順位が変わります。
でも、多くの整体・マッサージ店のサイトって、メニューを並べてるだけ。
具体的にその目的にどう応えられるのかわからないんです。
「この目的なら、ここが最適」って思わせるコンテンツを作ることが、整体・マッサージ店のWeb集客の鍵です。
それぞれの目的で、ユーザーがどんなニーズを持っているのか、整理してみましょう。
ユーザーのニーズ
痛み改善を目的とする人は、真剣に治療先を探してます。
腰痛がひどい、肩こりが辛い、頭痛が続く。
日常生活に支障が出てるから、しっかり治したい。
こういう切実なニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
症状別の施術内容を詳しく。
「腰痛の原因と当院の施術アプローチ」。
「肩こり解消の3ステップ」。
「頭痛の種類別対応」。
どんな症状にどう対応するか、具体的に説明。
治療計画の目安も示す。
「軽度の腰痛:週1回×4回程度」。
「慢性的な肩こり:週2回×8回程度」。
「症状により個人差があります」。
どれくらい通う必要があるか、目安を提示。
保険適用の説明も明確に。
「国家資格保有(柔道整復師)」。
「保険適用可能な症状:捻挫、打撲、挫傷など」。
「保険適用外:慢性的な肩こり、腰痛など」。
誤解のないよう、丁寧に説明。
コンテンツの見せ方
「痛み改善・治療」専用ページを作る。
症状別施術内容、治療計画、費用、保険適用。
痛み改善を求める人に必要な情報を集約。
実際の改善例も紹介。
「慢性腰痛が8回の施術で改善」。
ビフォーアフター、通院期間、お客様の声。
リアルな改善事例があると、期待が持てます。
初回カウンセリングの流れも。
「丁寧な問診→検査→施術→今後の計画説明」。
「初回は60分しっかり時間を取ります」。
真剣に向き合う姿勢を伝える。
ユーザーのニーズ
リラクゼーション目的の人は、癒しを求めてます。
仕事の疲れ、ストレス、日々の緊張。
ゆっくりリラックスして、リフレッシュしたい。
こういう前向きなニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
リラクゼーションメニューを充実。
「全身もみほぐし 60分 5,000円」。
「アロマオイルマッサージ 90分 8,000円」。
「ヘッドスパ 30分 3,000円」。
時間と価格をわかりやすく。
店内の雰囲気も詳しく伝える。
「落ち着いた照明」「癒しのBGM」。
「アロマの香り」「ふかふかのベッド」。
写真でリラックス空間を見せる。
個室やプライベート対応も。
「完全個室でプライバシー確保」。
「カップルルームあり」。
「女性専用タイム設定」。
安心してリラックスできる環境を伝える。
コンテンツの見せ方
「リラクゼーション」専用ページを作る。
メニュー、店内写真、雰囲気、予約方法。
癒しを求める人に必要な情報をまとめる。
お客様の感想も効果的。
「仕事の疲れが吹き飛びました」。
「ゆっくりできて最高のひととき」。
「また来たいと思える空間」。
リラックスできた体験談を紹介。
オプションメニューも。
「+ホットストーン」「+フットケア」。
「延長30分 2,500円」。
カスタマイズできる選択肢を提示。
ユーザーのニーズ
美容目的の人は、見た目の変化を求めます。
産後の骨盤矯正、小顔矯正、O脚改善。
機能的には問題ないけど、もっときれいになりたい。
こういう積極的なニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
美容メニューを詳しく。
「小顔矯正 1回 8,000円」。
「骨盤矯正 1回 6,000円」。
「美脚・O脚矯正 1回 7,000円」。
それぞれの施術内容と期待できる効果を説明。
ビフォーアフター写真も。
「小顔矯正の変化」。
「骨盤位置の改善」。
実際の変化が見えると、イメージしやすいです。
※個人差がある旨を明記。
回数券やコースの提案も。
「小顔矯正 5回コース 35,000円」。
「骨盤矯正 10回コース 55,000円」。
継続することで効果が出ることを伝える。
コンテンツの見せ方
「美容整体」専用ページを作る。
メニュー、施術内容、料金、ビフォーアフター。
美容目的の人に必要な情報を集約。
Instagramとの連携も。
「施術後の変化をインスタで紹介」。
「お客様の了承を得て掲載」。
ビジュアルで訴求する工夫を。
カウンセリング重視も伝える。
「まずはお悩みをお聞きします」。
「無理な勧誘は一切しません」。
「体験コースあり」。
試しやすい環境を整える。
ユーザーのニーズ
スポーツケア目的の人は、専門性を求めます。
ランナー、格闘技、ゴルフ、筋トレ。
競技に合わせたケアで、パフォーマンスを上げたい。
こういう専門的なニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
スポーツ別の対応を明記。
「ランナー向けケア」。
「格闘技・コンタクトスポーツ対応」。
「ゴルフパフォーマンス向上」。
どんなスポーツに対応できるか具体的に。
施術者の経歴もアピール。
「元アスリート」「スポーツトレーナー資格」。
「〇〇チームのサポート経験あり」。
スポーツの理解があることを示す。
怪我予防とコンディショニングも。
「試合前のコンディション調整」。
「練習後の疲労回復ケア」。
「怪我の予防メンテナンス」。
スポーツのサイクルに合わせた提案を。
コンテンツの見せ方
「スポーツケア」専用ページを作る。
対応スポーツ、施術内容、施術者経歴、料金。
アスリートに必要な情報をまとめる。
実際のアスリートの声も。
「パフォーマンスが上がった」。
「怪我が減った」「疲労回復が早くなった」。
競技者の声が、信頼につながります。
定期的なケアプランも。
「週1回のメンテナンス契約」。
「月4回 20,000円」。
継続的にサポートする体制を示す。
多くの整体・マッサージ店のサイトって、メニューを並べてるだけ。
全身もみほぐし、骨盤矯正、スポーツケア。
でも、それじゃあそれぞれの目的に合った情報が見つからない。
痛み改善の人には、治療計画と保険適用を。
リラクゼーション目的の人には、雰囲気と癒しを。
美容目的の人には、ビフォーアフターと継続効果を。
スポーツケアの人には、専門性と実績を。
それなのに、どのページも「コース紹介」が載ってるだけ。
どんな目的の人に向いてるのか、わからない。
ユーザーは、「自分の目的」に合った店が欲しいんです。
痛みを治したい人に、リラクゼーションの雰囲気写真ばかり見せても響かない。
美容目的の人に、保険適用の説明をしても興味ない。
スポーツケアを求める人に、一般的なマッサージの話では物足りない。
それぞれの目的に応じた情報提供ができないと、選ばれません。
ユーザーの目的を理解して、その時に必要な情報を、わかりやすく提供する。
これができて初めて、選ばれる整体・マッサージ店になるんです。
整体・マッサージを探してるユーザーは、それぞれ違う目的で来店します。
その目的に合った情報を、わかりやすく提供できる店が選ばれます。
それぞれの目的に必要なコンテンツを、専用ページで丁寧に説明する。
これができれば、「この目的ならここ」って選んでもらえます。
当社が提案しているユーザー目線で使いやすさを改善していくWeb集客メソッド「サイトスタイリング™」では、来店目的ごとにお客様が求める情報を徹底的に分析して、それぞれに応えるコンテンツ設計を行っています。
整体・マッサージ店なら、痛み改善、リラクゼーション、美容、スポーツケア、それぞれの目的でお客様が何を重視するのかを洗い出し、その情報を整理していきます。施術内容は具体的に、雰囲気は写真で魅力的に、料金は明確に、専門性は実績で。それぞれのコンテンツを、お客様が必要とする形で提供するんです。
整体・マッサージ選びは、体を預ける大切な選択。
だからこそ、失敗したくないんです。
「ここなら自分の目的に合ってる」って思ってもらえれば、来店につながります。
そのための第一歩が、目的別の情報をしっかり伝えること。
お客様の目的に寄り添った丁寧な情報提供が、選ばれる整体・マッサージ店を作り上げます。
整体・マッサージを選ぶとき、来店目的で求める情報は大きく変わります。
痛み改善、リラクゼーション、美容・スタイル改善、スポーツケア。
それぞれの目的で必要な情報を、わかりやすく提供することが大切です。
治療計画、雰囲気写真、ビフォーアフター、専門性。
こういった要素を、専用ページ、メニュー表、実績紹介など、適切な形で見せていく。
そうすれば、「ここに通いたい」って思ってもらえます。
あなたのお店のサイトは、それぞれの目的に応えられていますか?
整体・マッサージを探している人が本当に知りたい情報がありますか?
一度、それぞれの目的を想定して、じっくり見直してみてください。
きっと、改善できるポイントが見つかるはずです。
初回相談は無料です。
いつでもお気軽にお問い合わせください。
(この記事には画像があります。画像部分は外部ブログサイトで見れます。)
Webコンサルタントの松崎です。
少し前に書いた「歯医者を探す」ユーザー視点で見るWeb集客のポイントで、予防派と緊急派の二極化や、料金の不明確さについて書きました。
今回は、歯医者を探すユーザーの「患者のタイプ」に焦点を当てて、それぞれのニーズにどう応えるコンテンツを作ればいいのか、具体的に考えていきます。
歯医者を探すとき、一番大事なのが「どんなタイプの患者か」です。
定期検診を重視する人と、痛くなってから行く人では、見るポイントが全然違います。
見た目をきれいにしたい人と、子供を連れて行く親でも、優先順位が変わります。
でも、多くの歯科医院サイトって、診療科目を並べてるだけ。
具体的にそのタイプの患者にどんな対応ができるのかわからないんです。
「このタイプなら、ここが最適」って思わせるコンテンツを作ることが、歯科医院のWeb集客の鍵です。
それぞれのタイプで、ユーザーがどんなニーズを持っているのか、整理してみましょう。
ユーザーのニーズ
予防派の患者さんは、長期的な視点で歯医者を選びます。
虫歯になる前に、歯周病になる前に。
定期的にメンテナンスして、歯を守りたい。
だから、通いやすさと予防の専門性を重視してます。
解消するために必要なコンテンツ
予防歯科の取り組みを詳しく。
「3ヶ月に一度の定期検診をおすすめ」。
「専門の歯科衛生士によるクリーニング」。
「PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)」。
予防に力を入れてることを明確に。
定期検診の流れも説明。
「検診内容:虫歯チェック、歯周病チェック、クリーニング」。
「所要時間:約30分」「費用:保険適用で約3,000円」。
何をするか、どれくらいかかるか、具体的に示す。
通いやすさもアピール。
「駅から徒歩3分」「駐車場完備」。
「土曜日も診療」「平日は夜7時まで」。
継続して通える環境があることを伝える。
コンテンツの見せ方
「予防歯科・定期検診」専用ページを作る。
予防の重要性、検診内容、費用、予約方法。
予防派に必要な情報を集約。
定期検診のメリットも説明。
「早期発見で治療費を抑える」。
「歯の寿命を延ばす」「口臭予防にも効果」。
予防の価値を具体的に伝える。
患者さんの声も効果的。
「定期検診のおかげで虫歯ゼロが続いてます」。
「歯科衛生士さんが丁寧で気持ちいい」。
継続して通ってる人の声があると、安心できます。
ユーザーのニーズ
緊急派の患者さんは、とにかく焦ってます。
歯が痛くて眠れない、腫れてきた、詰め物が取れた。
すぐに何とかしてほしいから、今日対応してくれる歯医者を探してる。
こういう切実なニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
当日診療を強調。
「急患対応可」「当日予約受付中」。
「痛みのある方は優先的に診察」。
すぐに診てもらえることを前面に出す。
診療時間と電話番号を大きく表示。
「今すぐお電話ください」。
スマホならタップで発信できるように。
応急処置についても説明。
「まずは痛みを止める処置を行います」。
「その後の治療計画は相談して決めます」。
今日は応急処置だけでもいいことを伝える。
コンテンツの見せ方
「急な歯の痛みでお困りの方へ」専用ページを作る。
当日診療、持ち物、応急処置の内容、費用目安。
緊急時に必要な情報だけを集約。
よくある緊急症状も説明。
「ズキズキ痛む→虫歯の可能性」。
「歯茎が腫れた→歯周病、親知らずの炎症」。
「詰め物が取れた→応急処置可能」。
症状別の対応を示す。
初診の流れも簡潔に。
「保険証をお持ちください」。
「問診票記入→診察→応急処置→会計」。
「今後の治療は次回相談」。
スムーズに受診できることを示す。
ユーザーのニーズ
審美派の患者さんは、見た目の改善を求めます。
ホワイトニング、セラミック治療、矯正。
機能的には問題ないけど、もっときれいにしたい。
こういう前向きなニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
審美治療メニューを詳しく。
「ホワイトニング:オフィス/ホーム」。
「セラミック治療:詰め物、被せ物」。
「歯列矯正:ワイヤー、マウスピース」。
それぞれの特徴と適応を説明。
費用を明確に。
「オフィスホワイトニング 30,000円」。
「セラミッククラウン 1本 80,000円」。
「マウスピース矯正 400,000円〜」。
自由診療だからこそ、価格を明示。
ビフォーアフターも効果的。
「ホワイトニング前後の比較」。
「セラミック治療の仕上がり」。
実際の変化が見えると、イメージしやすいです。
コンテンツの見せ方
「審美歯科・ホワイトニング」専用ページを作る。
メニュー、費用、治療期間、症例写真。
見た目の改善を求める人に必要な情報を集約。
無料カウンセリングも案内。
「まずはご相談ください」。
「治療計画と見積もりを提示」。
「無理な勧誘は一切しません」。
相談しやすい雰囲気を伝える。
分割払いの案内も。
「デンタルローン対応」。
「月々○○円から治療可能」。
高額治療の支払いハードルを下げる。
ユーザーのニーズ
小児歯科を求める親は、子供への配慮を最重視します。
初めての歯医者、歯医者が怖い子。
無理やり治療するんじゃなくて、優しく対応してほしい。
こういう親心です。
解消するために必要なコンテンツ
小児歯科の対応を詳しく。
「子供に慣れたスタッフが対応」。
「無理な治療はしません」。
「治療の練習から始めます」。
子供に優しい対応を具体的に説明。
キッズスペースもアピール。
「待合室にキッズスペース」。
「おもちゃ、絵本、DVDあり」。
「ベビーカーで入れる診察室」。
子連れで来やすい環境を伝える。
予防プログラムも。
「フッ素塗布 1回 1,000円」。
「シーラント(奥歯の溝を埋める予防処置)」。
「歯磨き指導(親子で)」。
子供の虫歯予防に力を入れてることを示す。
コンテンツの見せ方
「小児歯科」専用ページを作る。
対応方針、キッズスペース、予防プログラム、費用。
子供を持つ親に必要な情報を集約。
院内の写真も多めに。
「明るい待合室」「カラフルな診察室」。
「子供が楽しめる工夫」。
雰囲気が伝わる写真を。
親の声も効果的。
「泣いて暴れる子供に、優しく接してくれた」。
「歯医者嫌いが治りました」。
「親も一緒に診てもらえて助かる」。
実際の体験談が、安心につながります。
多くの歯科医院サイトって、診療科目を並べてるだけ。
一般歯科、小児歯科、矯正歯科、審美歯科。
でも、それじゃあそれぞれのタイプに合った情報が見つからない。
予防派の人には、定期検診の内容と通いやすさを。
緊急派の人には、当日対応と応急処置を。
審美派の人には、治療メニューと費用を。
子供を連れてくる親には、子供への配慮と環境を。
それなのに、どのページも「診療案内」が載ってるだけ。
どんなタイプの患者に向いてるのか、わからない。
ユーザーは、「自分のタイプ」に合った歯医者が欲しいんです。
予防派の人に、急患対応をアピールしても響かない。
緊急派の人に、長期的な予防プランを説明しても今じゃない。
審美派の人に、一般的な虫歯治療の話ばかりしても興味ない。
それぞれのタイプに応じた情報提供ができないと、選ばれません。
ユーザーのタイプを理解して、その時に必要な情報を、わかりやすく提供する。
これができて初めて、選ばれる歯科医院になるんです。
歯医者を探してるユーザーは、それぞれ違うタイプの患者さんです。
そのタイプに合った情報を、わかりやすく提供できる歯科医院が選ばれます。
それぞれのタイプに必要なコンテンツを、専用ページで丁寧に説明する。
これができれば、「このタイプならここ」って選んでもらえます。
当社が提案している患者視点のサイトを最適化していくWeb集客メソッド「サイトスタイリング™」で、患者のタイプごとに求める情報を徹底的に分析して、それぞれに応えるコンテンツ設計を行っています。
歯科医院なら、予防派、緊急派、審美派、小児歯科、それぞれのタイプで患者さんが何を重視するのかを洗い出し、その情報を整理していきます。検診内容は詳しく、当日対応は明確に、費用は正直に、子供への配慮は具体的に。それぞれのコンテンツを、患者さんが必要とする形で提供するんです。
歯医者選びは、長く付き合う大切な選択。
だからこそ、自分にあったお医者さんを選びたい。
「ここなら自分に合ってる」って思ってもらえれば、来院につながります。
そのための第一歩が、タイプ別の情報をしっかり伝えること。
患者さんのタイプに寄り添った丁寧な情報提供が、選ばれる歯科医院を作り上げます。
歯医者を選ぶとき、患者のタイプで求める情報は大きく変わります。
予防派、緊急派、審美派、小児歯科。
それぞれのタイプで必要な情報を、わかりやすく提供することが大切です。
検診内容、当日対応、治療メニュー、子供への配慮。
こういった要素を、専用ページ、症例写真、費用表など、適切な形で見せていく。
そうすれば、「ここに通いたい」って思ってもらえます。
あなたの歯科医院のサイトは、それぞれのタイプに応えられていますか?
歯医者を探している人が本当に知りたい情報がありますか?
一度、それぞれのタイプを想定して、じっくり見直してみてください。
きっと、改善できるポイントが見つかるはずです。
初回相談は無料です。
いつでもお気軽にお問い合わせください。
(この記事には画像があります。画像部分は外部ブログサイトで見れます。)
Webコンサルタントの松崎です。
以前、このブログで 「ネットショップを無料チェックできるツール『EC-CHECKER』作りました!」 というお話や、それに続いてリリースした「英語版」についてもお伝えしました。
おかげさまで、公開直後からたくさんの方にお試しいただいています。
中には制作会社の方からも「これ便利!」なんて声をいただいたりしました。
本当に、作ってよかったなとしみじみ感じています。
そんなEC-CHECKERですが、この度ちょっと進化しました!
なんと、「LINE」からでもサクッと使えるようになりました。
それには、自分なりのちょっとした理由があります。
いつもお伝えしている通り、ECサイトも「接客」が命です。
でも、毎日自分のサイトを見ていると、どこがお客さんにとって不親切なのか、自分ではなかなか気づけないものなんですよね。
「わざわざPCを開いてツールを使うほどではないけど、ちょっと気になる……」 「移動中や、家でゴロゴロしている時に、パパッと自社サイトの状態を知りたい」
そんな風に、もっと日常の延長で、自分のサイトを「客観的に見る」きっかけを作ってほしい。
そう思って、誰もが毎日使っているLINEで動くように改良しました。
操作は、以前のツール以上にシンプル。
「ツールって聞くと難しそう……」という方もご安心を。
公式LINEを友だち追加する
診断したいサイトのURLをトーク画面にペタッと貼って送信!
これだけです。
すると、10秒ぐらいかな。パッと診断結果が返ってきます。
スマホでサクッと確認できるので、小難しい理屈抜きに「あ、ここがお客さんを困らせていたのかも」という気づきが得られるのが良いところ。 電車での移動中でも、寝っ転がりながらでも、スマホからLINEで簡単チェックできます。
ECサイトは、作って終わりではありません。
実店舗と同じで、毎日少しずつ「おもてなし」を整えていく必要があります。
「ここを少し直すだけで、もっとお客さんに喜んでもらえる!」 そんなポジティブな気づきを、このLINE版で見つけてもらえたら嬉しいです。
「とりあえず試してみようかな」という方は、ぜひこちらのリンクから友だち追加してみてください。
もちろん、これまで通り無料です。
あなたのネットショップが、より愛されるお店になるお手伝いができれば幸いです。
ぜひ一度、スマホからポチッと入力してみてくださいね!
(この記事には画像があります。画像部分は外部ブログサイトで見れます。)Webコンサルタントの松崎です。
先日公開した「病院・クリニックを探す」ユーザー視点で見るWeb集客のポイントで、Googleマップの口コミの重要性や、診療時間情報の見つけにくさについて書きました。
今回は、病院・クリニックを探すユーザーの「受診のきっかけ」に焦点を当てて、それぞれのニーズにどう応えるコンテンツを作ればいいのか、具体的に考えていきます。
病院を探すとき、一番大事なのが「どんなきっかけで受診するか」です。
急に具合が悪くなった人と、定期的に通院する人では、見るポイントが全然違います。
専門的な治療を求める人と、予防や健康管理目的の人でも、優先順位が変わります。
でも、多くの病院サイトって、診療科目を並べてるだけ。
具体的にそのきっかけでどんな診療を受けられるのかわからないんです。
「このきっかけなら、ここが最適」って思わせるコンテンツを作ることが、医療機関のWeb集客の鍵です。
それぞれのきっかけで、ユーザーがどんなニーズを持っているのか、整理してみましょう。
ユーザーのニーズ
急に具合が悪くなった人は、とにかく焦ってます。
高熱が出た、腹痛がひどい、怪我をした。
すぐに診てほしいから、今日対応してくれる病院を探してる。
こういう緊急性の高いニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
本日の診療状況をリアルタイムで。
「本日診療中」「受付終了まであと○時間」。
「混雑状況:やや混雑」。
今すぐわかる情報を目立つ場所に。
当日受診の案内も明確に。
「当日予約受付中」「予約なしでも受診可」。
「待ち時間目安:約30分」。
すぐに診てもらえるかどうか、はっきり示す。
症状から診療科がわかるガイドも。
「こんな症状なら内科」。
「この症状なら整形外科」。
迷わず適切な診療科を選べるように。
コンテンツの見せ方
「急な体調不良の方へ」専用ページを作る。
本日の診療状況、持ち物、症状別診療科ガイド。
緊急時に必要な情報だけを集約。
電話番号を大きく表示。
「今すぐお電話ください」。
スマホならタップで発信できるように。
初診の流れも簡潔に。
「保険証をお持ちください」。
「問診票は来院後に記入」。
「受付→待合→診察→会計」。
不安を減らす情報を簡潔に。
ユーザーのニーズ
慢性疾患で継続通院する人は、長期的な視点で選びます。
糖尿病、高血圧、喘息。
月に一度、定期的に通うことになる。
だから、通いやすさと信頼関係が何より大事。
解消するために必要なコンテンツ
アクセスの良さを強調。
「〇〇駅から徒歩3分」。
「駐車場10台完備」「雨の日も濡れない連絡通路」。
通いやすさを具体的に示す。
診療方針と医師の考え方も。
「患者さんの生活に寄り添った治療を」。
「無理のない治療計画を一緒に考えます」。
長く付き合える安心感を伝える。
予約システムの利便性もアピール。
「オンライン予約で待ち時間短縮」。
「定期通院の方は次回予約を取りやすく」。
「処方箋はFAXで薬局へ送信可能」。
継続通院の負担を減らす工夫を。
コンテンツの見せ方
「生活習慣病・慢性疾患の方へ」専用ページを作る。
通院の流れ、診療方針、予約システム、処方箋対応。
継続通院に必要な情報をまとめる。
実際の治療例も紹介。
「糖尿病の患者さんとの10年」。
「無理なく血糖値をコントロール」。
長期的な治療実績があると、安心できます。
患者さんの声も効果的。
「先生が親身に話を聞いてくれる」。
「通いやすい場所で助かってます」。
リアルな声が、信頼につながります。
ユーザーのニーズ
専門的な治療を求める人は、慎重に選びます。
なかなか治らない症状、手術の必要性。
一般的な治療では改善しない。
だから、専門性と実績を重視してます。
解消するために必要なコンテンツ
専門分野を具体的に明記。
「〇〇専門外来」「〇〇年の経験」。
「〇〇学会認定専門医」。
専門性の根拠を示す。
可能な検査・治療を詳しく。
「最新の〇〇検査機器導入」。
「〇〇治療に対応」「日帰り手術可能」。
どこまで対応できるか明確に。
実績も数字で示す。
「年間〇〇件の治療実績」。
「〇〇の治療成功率〇〇%」(医療広告ガイドラインに注意)。
「他院からの紹介患者多数」。
信頼の根拠を提示。
コンテンツの見せ方
「専門外来」専用ページを作る。
専門分野、医師の経歴、検査・治療内容、実績。
専門的な治療を求める人に必要な情報を集約。
セカンドオピニオンの案内も。
「他院で診断を受けた方へ」。
「セカンドオピニオン外来あり」。
「完全予約制、相談料〇〇円」。
選択肢を提供する姿勢を示す。
論文や学会発表の実績も。
「〇〇学会で発表」。
「医学誌〇〇に論文掲載」。
専門性の高さを裏付ける情報を。
ユーザーのニーズ
予防や健康管理で受診する人は、計画的に考えてます。
会社の健康診断、インフルエンザ予防接種。
病気になる前に、健康を維持したい。
こういう前向きなニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
健康診断メニューを詳しく。
「一般健康診断 5,000円」。
「人間ドック基本コース 30,000円」。
「オプション検査あり」。
メニューと料金を明確に。
予防接種の情報も充実。
「インフルエンザ予防接種 3,500円」。
「予約不要、在庫あり」。
「接種可能期間:10月〜1月」。
すぐに予約・接種できる情報を。
予約カレンダーも効果的。
「健康診断予約状況」。
「○:空きあり」「△:残りわずか」。
予約の取りやすさが一目でわかる。
コンテンツの見せ方
「予防・健康管理」専用ページを作る。
健康診断メニュー、予防接種、料金表、予約方法。
予防目的の人に必要な情報をまとめる。
健康情報コラムも充実。
「生活習慣病予防のポイント」。
「年代別の健康管理」。
予防意識の高い人に役立つ情報を提供。
オンライン問診票も便利。
「事前に入力で当日スムーズ」。
「健康診断の問診票をダウンロード」。
来院前の準備ができる仕組みを。
多くの病院サイトって、診療科目を並べてるだけ。
内科、外科、整形外科、皮膚科。
でも、それじゃあそれぞれのきっかけに合った情報が見つからない。
急いでる人には、今日診られるかと待ち時間を。
継続通院する人には、通いやすさと信頼関係を。
専門治療を求める人には、専門性と実績を。
予防目的の人には、メニューと料金を。
それなのに、どのページも「診療科目」「診療時間」が載ってるだけ。
どんな症状に対応してるか、どんな人に向いてるか、わからない。
ユーザーは、「自分の受診のきっかけ」に合った情報が欲しいんです。
急いでる人に、医師の詳しい経歴を長々と見せても意味がない。
専門治療を求める人に、「内科一般」としか書いてなければ不安。
それぞれのきっかけに応じた情報提供ができないと、選ばれません。
ユーザーの状況を理解して、その時に必要な情報を、わかりやすく提供する。
これができて初めて、選ばれる医療機関になるんです。
病院を探してるユーザーは、それぞれ違うきっかけで検索してます。
そのきっかけに合った情報を、わかりやすく提供できる医療機関が選ばれます。
それぞれのきっかけに必要なコンテンツを、専用ページで丁寧に説明する。
これができれば、「このきっかけならここ」って選んでもらえます。
当社が提案している患者目線で最適化を行うWeb集客メソッド「サイトスタイリング™」で、受診のきっかけごとに患者さんが求める情報を徹底的に分析して、それぞれに応えるコンテンツ設計を行っています。
医療機関なら、緊急時、継続通院、専門治療、予防目的、それぞれのきっかけで患者さんが何を重視するのかを洗い出し、その情報を整理していきます。診療状況はリアルタイムで、専門性は具体的に、料金は明確に、予約は簡単に。それぞれのコンテンツを、患者さんが必要とする形で提供するんです。
病院選びは、健康という大切な問題に関わる選択。
だからこそ、失敗したくないんです。
「ここなら安心して受診できる」って思ってもらえれば、来院につながります。
そのための第一歩が、きっかけ別の情報をしっかり伝えること。
患者さんの状況に寄り添った丁寧な情報提供が、選ばれる医療機関を作り上げます。
病院・クリニックを選ぶとき、受診のきっかけで求める情報は大きく変わります。
急な体調不良、継続通院、専門治療、予防・健康管理。
それぞれのきっかけで必要な情報を、わかりやすく提供することが大切です。
診療状況、アクセス、専門性、料金表。
こういった要素を、専用ページ、症状別ガイド、実績紹介など、適切な形で見せていく。
そうすれば、「ここで診てもらいたい」って思ってもらえます。
あなたの医療機関のサイトは、それぞれのきっかけに応えられていますか?
病院を探している人が本当に知りたい情報がありますか?
一度、それぞれのきっかけを想定して、じっくり見直してみてください。
きっと、改善できるポイントが見つかるはずです。
初回相談は無料です。
いつでもお気軽にお問い合わせください。
(この記事には画像があります。画像部分は外部ブログサイトで見れます。)
Webコンサルタントの松崎です。
少し前にユーザー視点で見る記事で投稿した「家具・インテリアを購入する」ユーザー視点で見るWeb集客のポイントで、サイズ問題や組み立て式の不安について書きました。
今回は、家具・インテリアを購入するユーザーの「購入目的」に焦点を当てて、それぞれのニーズにどう応えるコンテンツを作ればいいのか、具体的に考えていきます。
家具を購入するとき、一番大事なのが「何のために買うか」です。
新生活で一式揃える人と、模様替えで一部を変える人では、見るポイントが全然違います。
子供の成長に合わせて買う人と、収納を増やしたい人でも、優先順位が変わります。
でも、多くの家具サイトって、カテゴリ別に商品を並べてるだけ。
具体的にその目的でどんな家具を選べばいいのかわからないんです。
「この目的なら、この組み合わせ」って思わせるコンテンツを作ることが、家具販売集客の鍵です。
それぞれの目的で、ユーザーがどんなニーズを持っているのか、整理してみましょう。
ユーザーのニーズ
新生活を始める人は、ゼロから家具を揃えます。
大学生の一人暮らし、新婚生活、転勤での引っ越し。
限られた予算で、必要なものを効率よく買いたい。
こういう計画的なニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
新生活セットを提案。
「一人暮らしスタートセット 15万円」。
「ベッド・デスク・チェスト・カーテン・ラグ」。
必要な家具をまとめたパッケージ。
部屋の広さ別にコーディネート。
「6畳ワンルーム向けレイアウト」。
「8畳1K向けレイアウト」。
家具の配置例を図解で示す。
統一感のあるスタイル提案も。
「北欧スタイルセット」「ナチュラルスタイルセット」。
「モダンスタイルセット」。
テイストを揃えた組み合わせを提案。
コンテンツの見せ方
「新生活応援」専用ページを作る。
セット商品、部屋別レイアウト、配送・組み立てサービス。
新生活に必要な情報を集約。
3Dシミュレーターも効果的。
「部屋の間取りを入力→家具を配置してみる」。
実際の部屋に置いたイメージが湧く。
配送スケジュールも明確に。
「引っ越し日に合わせて配送」。
「まとめて配送で送料お得」。
新生活の準備がスムーズに進むように。
ユーザーのニーズ
模様替えをしたい人は、部分的に変えたいんです。
ソファだけ、カーテンだけ、ラグだけ。
今ある家具と合わせて、雰囲気を変えたい。
こういう慎重なニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
既存家具との合わせ方を提案。
「ダークブラウンの家具に合うソファ」。
「ホワイト系インテリアに映えるラグ」。
色や素材の相性を具体例で示す。
プチ模様替えアイデアも。
「クッションカバーを変えるだけ」。
「照明を変えて雰囲気アップ」。
「壁に棚を追加して収納力UP」。
低予算でできる提案を。
ビフォーアフター事例も充実。
「ソファを変えただけでこんなに印象が変わる」。
費用○万円、変えた家具、お客様の声。
実際の変化がわかると、イメージしやすいです。
コンテンツの見せ方
「模様替え特集」ページを作る。
予算別、アイテム別、スタイル別の提案。
部分的に変える人に役立つ情報を。
カラーコーディネートガイドも。
「ブラウン系」「グレー系」「ホワイト系」。
それぞれに合う家具・ファブリックを紹介。
お試ししやすい返品制度も。
「30日間返品保証」。
「実際に部屋に置いて確かめられます」。
失敗を恐れず、試せる安心感を。
ユーザーのニーズ
子供のための家具を買う親は、慎重です。
学習机、ベッド、本棚。
成長が早いから、長く使えるものを選びたい。
でも、安全性も妥協できない。
解消するために必要なコンテンツ
成長に合わせた提案を年齢別に。
「小学校入学時:学習机・チェア」。
「中学生:ベッド・収納」。
「高校生:大人まで使える家具」。
年齢ごとに必要な家具を提案。
安全性の説明も詳しく。
「角丸加工で怪我防止」。
「転倒防止金具付き」「F☆☆☆☆で安心」。
「耐荷重○○kg」。
子供が使っても安全な理由を明記。
高さ調整機能もアピール。
「チェアは身長に合わせて5段階調整」。
「デスクの天板も高さ変更可能」。
成長に合わせて使える機能を説明。
コンテンツの見せ方
「キッズ・学習家具」専用ページを作る。
年齢別提案、安全性情報、成長対応機能。
子供のための家具に必要な情報を集約。
実際の使用例も写真で。
「小学1年生が使ってる様子」。
「6年間使っても丈夫です(お客様の声)」。
長期使用の実例があると、安心できます。
親の声も効果的。
「姿勢が良くなりました」。
「集中して勉強するようになった」。
実際の効果が伝わると、購入の決め手に。
ユーザーのニーズ
収納を増やしたい人は、機能性を最重視します。
物が増えて部屋が狭い、収納が足りない。
でも、ただ収納を増やすだけじゃなくて、おしゃれさも欲しい。
こういう実用的なニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
スペース別の収納提案。
「狭い玄関に→スリムシューズラック」。
「クローゼットが小さい→突っ張りハンガーラック」。
「リビングが散らかる→収納付きテレビボード」。
場所ごとの悩みと解決策をセットで。
収納力を数字で示す。
「文庫本○○冊収納可能」。
「A4ファイル○○個入ります」。
「衣類○○着掛けられます」。
具体的な数字で、収納力がわかる。
多機能家具もアピール。
「ベッド下収納付き」。
「デスク兼用ドレッサー」。
「折りたたみ式テーブル」。
一つで二役の家具を提案。
コンテンツの見せ方
「収納・スペース活用」専用ページを作る。
悩み別提案、収納力比較、多機能家具特集。
収納重視の人に役立つ情報を集約。
ビフォーアフター事例も効果的。
「散らかっていた部屋が→スッキリ」。
どの収納家具を使って、どう変わったか。
実際の改善例を見せる。
サイズ別にも提案。
「幅30cm以下のスリム収納」。
「高さ180cm以上の大容量収納」。
スペースに合わせた選び方を。
多くの家具サイトって、商品カテゴリ別に並べてるだけ。
ソファ、ベッド、テーブル、収納って分類されてても、それじゃあ目的に合った選び方がわからない。
新生活の人には、セット提案とレイアウト例を。
模様替えの人には、既存家具との合わせ方を。
子供のための家具を探す人には、安全性と成長対応を。
収納を増やしたい人には、スペース別の提案を。
それなのに、どのページも「商品スペック」が載ってるだけ。
サイズと素材と価格。
確かに必要な情報だけど、それだけじゃ選べないんです。
ユーザーは、「自分の目的」に合った家具が欲しいんです。
新生活なのに、単品商品をいくつも見せられても困る。
模様替えなのに、全く統一感のない商品を並べられても迷う。
子供のためなのに、安全性の情報がなければ不安。
それぞれの目的に応じた情報提供ができないと、購入につながりません。
ユーザーの目的を理解して、その時に必要な家具と情報を、わかりやすく提案する。
これができて初めて、選ばれるサイトになるんです。
家具を購入するユーザーは、それぞれ違う目的で買い物してます。
その目的に合った情報を、わかりやすく提供できるサイトが選ばれます。
新生活→セット提案、レイアウト例、配送スケジュール。
模様替え→既存家具との合わせ方、ビフォーアフター、返品保証。
子供の成長→年齢別提案、安全性、成長対応機能。
収納重視→スペース別提案、収納力数値、多機能家具。
それぞれの目的に必要なコンテンツを、専用ページで丁寧に説明する。
これができれば、「この目的ならここ」って選んでもらえます。
当社が提案しているユーザー目線のWeb集客メソッド「サイトスタイリング™」では、購入目的ごとにユーザーが求める情報を徹底的に分析して、それぞれに応えるコンテンツ設計を行っています。
家具販売なら、新生活、模様替え、子供の成長、収納重視、それぞれの目的でユーザーが何を重視するのかを洗い出し、その情報を整理していきます。セット提案はわかりやすく、レイアウトは視覚的に、安全性は詳しく丁寧に、収納力は数字で明確に。それぞれのコンテンツを、ユーザーが必要とする形で提供するんです。
家具は、長く使うもの。
だからこそ、失敗したくないんです。
「ここなら自分の目的に合った家具が見つかる」って思ってもらえれば、購入につながります。
そのための第一歩が、目的別の情報をしっかり伝えること。
ユーザーの目的に寄り添った丁寧な情報提供が、選ばれる家具サイトを作り上げます。
家具・インテリアを購入するとき、購入目的で求める情報は大きく変わります。
新生活、模様替え、子供の成長、収納重視。
それぞれの目的で必要な情報を、わかりやすく提供することが大切です。
セット提案、コーディネート例、安全性情報、収納力比較。
こういった要素を、専用ページ、レイアウト図、ビフォーアフターなど、適切な形で見せていく。
そうすれば、「ここで買いたい」って思ってもらえます。
あなたのサイトは、それぞれの目的に応えられていますか?
家具を探している人が本当に知りたい情報がありますか?
一度、それぞれの目的を想定して、じっくり見直してみてください。
きっと、改善できるポイントが見つかるはずです。
初回相談は無料です。
いつでもお気軽にお問い合わせください。
(この記事には画像があります。画像部分は外部ブログサイトで見れます。)