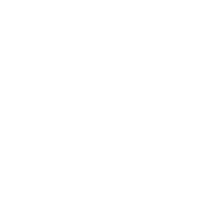Webコンサルタントの松崎です。
検索行動のシリーズ記事で取り上げた「介護サービスを探す」ユーザー視点で見るWeb集客のポイントで、料金の不透明さや、空き状況がわからない問題について書きました。
今回は、介護サービスを探すユーザーの「サービスの種類」に焦点を当てて、それぞれのニーズにどう応えるコンテンツを作ればいいのか、具体的に考えていきます。
介護サービス選びは「どんなサービスを求めるか」で全部変わる
介護サービスを探すとき、一番大事なのが「どんなサービスを求めるか」です。
日中だけ預けたい人と、24時間施設で看てほしい人では、見るポイントが全然違います。
自宅での介護を支えてほしい人と、短期間だけ利用したい人でも、優先順位が変わります。
でも、多くの介護事業者サイトって、提供サービスを並べてるだけ。
具体的にそのサービスでどんな生活になるのかわからないんです。
「このサービスなら、ここが最適」って思わせるコンテンツを作ることが、介護事業者のWeb集客の鍵です。
サービスの種類別で見るユーザーのニーズ
それぞれのサービスで、ユーザーがどんなニーズを持っているのか、整理してみましょう。
サービス①:デイサービス(通所介護)
ユーザーのニーズ
- 日中だけ預かってほしい
- リハビリをしてほしい
- 同世代と交流させたい
- 入浴サービスを受けたい
- 送迎はしてくれるか
デイサービスを探す家族は、在宅介護を続けたいんです。
夜は家で過ごすけど、日中は預かってほしい。
仕事に行く間、安心して任せられる場所が欲しい。
こういう在宅介護支援のニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
一日の流れを詳しく。
「9:00 お迎え」「10:00 健康チェック・入浴」。
「12:00 昼食」「13:00 レクリエーション」。
「15:00 おやつ・機能訓練」「16:00 お送り」。
具体的な過ごし方を時間割で示す。
送迎エリアと時間も明確に。
「送迎対応エリア:〇〇市全域」。
「お迎え時間:8:30〜9:30の間」。
「お送り時間:16:00〜17:00の間」。
送迎の詳細がわかると、利用しやすい。
食事とレクリエーションも。
「管理栄養士による献立」。
「食事形態:普通食、きざみ食、ペースト食」。
「レクリエーション:体操、歌、ゲーム、季節行事」。
写真で楽しそうな雰囲気を伝える。
コンテンツの見せ方
「デイサービス」専用ページを作る。
一日の流れ、送迎エリア、食事・入浴、レクリエーション。
デイサービスに必要な情報を集約。
実際の様子を動画で。
「レクリエーションの様子」。
「楽しく体操する利用者さん」。
動画があると、雰囲気が伝わりやすいです。
利用者家族の声も。
「母が毎日楽しみに通ってます」。
「仕事中も安心して任せられます」。
実際の満足度が伝わると、選びやすいです。
サービス②:訪問介護(ホームヘルプ)
ユーザーのニーズ
- 自宅での生活を支えてほしい
- 身体介護をしてほしい
- 家事援助をしてほしい
- 夜間・早朝も対応できるか
- 信頼できるヘルパーか
訪問介護を探す家族は、住み慣れた家での生活を守りたいんです。
施設には入れたくない、本人も自宅がいいと言ってる。
でも、家族だけでは限界。
こういう在宅支援のニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
サービス内容を具体的に。
「身体介護:食事介助、排泄介助、入浴介助、着替え」。
「生活援助:掃除、洗濯、買い物、調理」。
何をしてくれるか、何ができないか、明確に。
対応時間帯も明記。
「24時間対応可能」。
「早朝(6:00〜8:00)、夜間(18:00〜22:00)」。
「深夜(22:00〜6:00)も対応」。
時間の柔軟性を示す。
ヘルパーの紹介も。
「経験豊富なヘルパーが担当」。
「介護福祉士資格保有者多数」。
「定期的な研修で質を維持」。
顔写真付きで安心感を。
コンテンツの見せ方
「訪問介護」専用ページを作る。
サービス内容、対応時間、料金例、ヘルパー紹介。
訪問介護に必要な情報をまとめる。
利用シーン別の説明も。
「一人暮らしの父のための週3回訪問」。
「老老介護の夫婦のための毎日訪問」。
具体的なケースで利用イメージを。
安心のポイントも伝える。
「担当ヘルパー制で顔なじみに」。
「緊急時の連絡体制」。
「個人情報の厳守」。
信頼関係が築けることを示す。
サービス③:施設入所(特養・有料老人ホーム)
ユーザーのニーズ
- 24時間介護してほしい
- 安心して暮らせる場所か
- 費用はいくらかかるか
- 医療体制は整っているか
- 入居までどれくらいかかるか
施設入所を検討する家族は、重い決断をしてます。
在宅では限界、でも施設に入れることへの罪悪感。
本人の気持ち、経済的負担、すべてを考えた上での選択。
こういう切実なニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
施設での一日を詳しく。
「6:30 起床」「7:00 朝食」。
「午前中 入浴、機能訓練、レクリエーション」。
「12:00 昼食」「午後 散歩、趣味活動、休息」。
「18:00 夕食」「21:00 就寝」。
どんな生活を送るか、具体的に示す。
料金を明確に。
「月額利用料:15万円(介護度3の場合)」。
「内訳:居住費5万円、食費4万円、介護費6万円」。
「入居一時金:不要(または○○万円)」。
トータルでいくらか、わかりやすく。
医療体制も詳しく。
「看護師24時間配置」。
「協力医療機関:〇〇病院」。
「訪問診療:月2回」。
医療面の安心を伝える。
コンテンツの見せ方
「施設入所」専用ページを作る。
施設の一日、居室タイプ、料金、医療体制、入居の流れ。
施設入所に必要な情報を集約。
居室と共用スペースの写真も。
「個室の様子」「食堂」「浴室」。
「リビング」「庭」。
実際の生活空間が見えると、イメージしやすいです。
入居者・家族の声も。
「最初は罪悪感があったけど、ここに入れて良かった」。
「スタッフが親身で、母も笑顔が増えた」。
入所後の満足度が伝わると、決断しやすいです。
サービス④:ショートステイ(短期入所)
ユーザーのニーズ
- 一時的に預かってほしい
- 介護者の休息が必要
- 冠婚葬祭で留守にする
- 退院後の様子見に使いたい
- 急な利用は可能か
ショートステイを探す家族は、一時的な支援が必要なんです。
介護疲れで倒れそう、出張で留守にする。
数日だけでも預かってもらえれば、何とかなる。
こういうレスパイトケアのニーズです。
解消するために必要なコンテンツ
利用期間と予約方法を明確に。
「1泊2日から利用可能」。
「最長30日まで連続利用可」。
「予約:1ヶ月前から受付」。
「空き状況:お電話でお問い合わせください」。
柔軟に対応できることを伝える。
料金も一泊単位で。
「1泊2日:8,000円(介護度2の場合)」。
「食事代:1,500円/日」。
「その他:日用品持ち込みまたは実費」。
短期利用の料金がわかるように。
持ち物リストも。
「着替え(〇日分)」「内服薬」。
「愛用の寝具(必要な方のみ)」。
「入れ歯洗浄剤」「その他日用品」。
準備がスムーズにできる情報を。
コンテンツの見せ方
「ショートステイ」専用ページを作る。
利用期間、料金、一日の流れ、持ち物リスト。
ショートステイに必要な情報をまとめる。
よくある利用ケースも。
「介護者の休息のために月1回3泊4日」。
「家族旅行の間の5泊6日」。
「退院直後のお試し1泊2日」。
具体的な使い方を示す。
初めての方へのメッセージも。
「初めてのショートステイで不安な方へ」。
「施設の雰囲気に慣れるまでスタッフがサポート」。
「見学・お試し利用も可能です」。
安心して利用できることを伝える。
従来の介護事業者サイトで見落とされていること
多くの介護事業者サイトって、提供サービスを並べてるだけ。
デイサービス、訪問介護、施設入所、ショートステイ。
でも、それじゃあそれぞれのサービスでどんな生活になるのかわからない。
デイサービスを探す人には、一日の流れと送迎を。
訪問介護を探す人には、サービス内容と対応時間を。
施設入所を検討する人には、料金と医療体制を。
ショートステイを使いたい人には、予約方法と柔軟性を。
それなのに、どのページも「サービス内容」が載ってるだけ。
どんな人に向いてるのか、どんな生活になるのか、わからない。
ユーザーは、「自分が求めるサービス」の詳しい情報が欲しいんです。
デイサービスを探してる人に、施設入所の長い説明をしても意味がない。
訪問介護を求める人に、通所の話をしても響かない。
ショートステイを使いたい人に、長期入所の料金を見せても不要。
それぞれのサービスに応じた情報提供ができないと、選ばれません。
ユーザーのニーズを理解して、そのサービスで必要な情報を、わかりやすく提供する。
これができて初めて、選ばれる介護事業者になるんです。
これからの介護事業者集客は「サービス種類別の情報提供」がカギ
介護サービスを探してるユーザーは、それぞれ違うサービスを求めてます。
そのサービスに合った情報を、わかりやすく提供できる事業者が選ばれます。
- デイサービス→一日の流れ、送迎エリア、レクリエーション。
- 訪問介護→サービス内容、対応時間、ヘルパー紹介。
- 施設入所→料金、医療体制、居室、入居の流れ。
- ショートステイ→利用期間、予約方法、持ち物リスト。
それぞれのサービスに必要なコンテンツを、専用ページで丁寧に説明する。
これができれば、「このサービスならここ」って選んでもらえます。
当社が提案している利用者家族のニーズに寄り添ってサイトを最適化するWeb集客メソッド「サイトスタイリング™」は、サービスの種類ごとに家族が求める情報を徹底的に分析して、それぞれに応えるコンテンツ設計を行います。
介護事業者なら、デイサービス、訪問介護、施設入所、ショートステイ、それぞれのサービスで家族が何を重視するのかを洗い出し、その情報を整理していきます。一日の流れは時間割で、料金は内訳で明確に、スタッフは顔が見えるように、医療体制は具体的に。それぞれのコンテンツを、家族が必要とする形で提供するんです。
介護サービス選びは、家族にとって重く切実な選択。
だからこそ、失敗したくないんです。
「ここなら安心して任せられる」って思ってもらえれば、利用につながります。
そのための第一歩が、サービス種類別の情報をしっかり伝えること。
家族の不安に寄り添った丁寧な情報提供が、選ばれる介護事業者を作り上げます。
まとめ
介護サービスを選ぶとき、サービスの種類で求める情報は大きく変わります。
デイサービス、訪問介護、施設入所、ショートステイ。
それぞれのサービスで必要な情報を、わかりやすく提供することが大切です。
一日の流れ、料金内訳、医療体制、予約方法。
こういった要素を、専用ページ、写真、動画、利用者の声など、適切な形で見せていく。
そうすれば、「ここに任せたい」って思ってもらえます。
あなたの事業所のサイトは、それぞれのサービスに応えられていますか?
介護サービスを探している家族が本当に知りたい情報がありますか?
一度、それぞれのサービスを想定して、じっくり見直してみてください。
きっと、改善できるポイントが見つかるはずです。
初回相談は無料です。
いつでもお気軽にお問い合わせください。
(この記事には画像があります。画像部分は外部ブログサイトで見れます。)