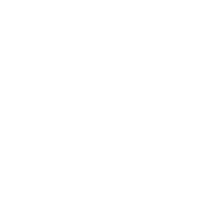日傘 手染め注染日傘(スレン仕様)
ホームページに人を集めるだけではダメ!お客様の気持ちを理解しよう
ホームページはあるのに思うような効果が出ていない、広告にお金をかけているのに問い合わせが増えない、そんな悩みをよく相談いただきます。
これは特別なことではなく、たくさんの中小企業が同じような悩みを抱えています。でも、その原因は意外と単純なところにあるかもしれません。

こんな悩みを解決するための大切な考え方「お客様の気持ちを理解すること」について、わかりやすくご説明します。この考え方を取り入れるだけで、ホームページの効果は大きく変わる可能性があります。
なぜホームページに人を集めるだけでは足りないのか
多くの中小企業がホームページを持ち、そこにたくさん見込み客を集めようと様々な取り組みをしています。
Google広告を出したり、SNSで情報発信したり、ホームページの文章を工夫したり…。これらの取り組みは確かに大切なのですが、実はそれだけでは不十分なのです。
たとえば、お店を開くことを考えてみてください。
たくさんの広告を出して大勢のお客様に来店してもらうことももちろん大切です。
しかし、お店に入ったお客様が「商品が見つけにくい」「店内が暗くて雰囲気が..」「欲しい情報が聞けない」「店内(店外)が汚れている」などと感じれば、何も買わずに帰ってしまいますよね。
ホームページも同じです。
いくら多くの人を集めても、その人たちが「欲しい情報が見つからない」「使いづらい」と感じれば、すぐに離れてしまいます。
そして一度そう思われてしまうと、見にくい使いにくいホームページには二度と訪問しないので、どんな集客手段をとっても、訪問してもらえなくなってしまいます。
「人を集めること」と同じくらい、あるいはそれ以上に「訪れた人に満足してもらうこと」が大切なのです。なので、お客様がどんな気持ちでホームページを見ているのか、何を求めているのかをしっかりと理解する必要があります。
お客様の気持ちを理解することの大切さ
「お客様の気持ちを理解する」と聞くと、難しく感じるかもしれません。でも実は、私たちは日常生活の中で、相手の気持ちを理解する努力をいつもしています。
たとえば、家族にプレゼント渡そうとする時、「何が好きだろう?」「どんなものを持っていて、何が必要だろう?」と考えますよね。これが「相手理解」の一番わかりやすい例じゃないかなと思います。
ホームページを訪れるお客様についても同じように考えることが大切です。
「どんな悩みを持っているのだろう?」「何を知りたいと思っているのだろう?」「どうやって情報を探しているのだろう?」と、お客様の立場になって想像してみることが、効果的なホームページ作りにとても重要なのです。
実は多くの中小企業が、自分たちが伝えたいことを一方的に発信するだけで、お客様が本当に知りたいことに応えていません。お客様の気持ちを理解し、それに応えることができれば、自然とホームページの効果は高まっていきます。
そして、お客様に役立つ情報がたくさん掲載されているホームページは、検索エンジンも高く評価するようになるので、検索順位が上昇し、より多くの人が訪問するようになります。
お客様の気持ちを理解するための3つの方法
では具体的に、どうすればお客様の気持ちを理解できるのでしょうか。特別な道具や専門知識がなくても始められる3つの方法をご紹介します。
1. お客様の声に耳を傾ける
まず大切なのは、実際のお客様の声に耳を傾けることです。日々の営業活動やお問い合わせの中には、たくさんの「お客様の本音」が隠れています。
- お客様との会話(店舗や電話での対応時)
- お問い合わせの内容(メールや問い合わせフォームから)
- SNSでのコメントや反応
- 営業担当者からの報告
たとえば、よくある質問を集めてみると「お客様が困っていること」「お客様が理解されていないポイント」「お客様が迷いやすいポイント」などが見えてきます。
「料金体系がわかりにくい」という声が多ければ、その部分の説明を充実させるべきかもしれません。「商品Aと商品Bの違いを教えてほしい」という質問が多ければ、比較表を作成するとお客様の要望に応えられる改善ができるようになります。
「お客様の生の声」から得られる気づきは、ホームページの改善に直結します。なぜなら、それはまさに「お客様が知りたいと思っていること」だからです。
2. お客様の行動パターンを観察する
お客様がどのように行動するのかを理解することも重要です。
商品を選ぶとき、サービスを利用するとき、お客様はどのような順序で考え、どのようなポイントを重視しているか。
たとえば、あるお店で「お客様はまず価格を確認し、次に機能を比較している」ということがわかれば、ホームページでも同じ順序で情報を並べるとこれまでより理解してもらいやすくなります。
「購入するきっかけが、他のお客様の口コミだった」とわかれば、口コミ情報を目立つ位置に移動させて、これまでより多くの口コミを配置するのが良いです。
こうしたお客様の行動パターンがわかると、お客様が自然に情報を見つけられ、理解してもらいやすいホームページになります。お客様は「探していた情報がすぐに見つかる」と感じると、好感度が高まりますし、購入や問い合わせにつながりやすくなります。
3. アクセス情報とお客様の声を組み合わせて考える
アクセス解析とお客様の声を組み合わせることも重要です。
ホームページのアクセス解析ツールを使うと、「どのページをよく見られているか」「どこで離脱しているか」といった数字がわかります。
しかし、数字だけでは、なぜそのページがよく見られているのか、なぜそのページで離脱するのかがはっきりとわかりません。たとえば、あるページの滞在時間が長い理由は、「内容が充実していて読み込んでいる」のかもしれませんし、「情報が整理されておらず探すのに時間がかかっている」のかもしれません。
そこで、アクセス情報の分析とお客様の声を組み合わせることで、より正確な理解が可能になります。「このページの滞在時間が長いのはなぜ?」という疑問に対して、お客様の声から「写真が多くて参考になるから」という答えが得られれば、他のページにも写真を増やすという改善策を行うことができます。
このように、数字という「事実」とお客様の声という「理由」を組み合わせることで、より効果的な改善ができるようになります。
お客様理解に基づいたホームページ改善の実践例
お客様の気持ちを理解した上で、具体的にホームページをどのように改善すればよいのでしょうか。いくつか取り組み方を紹介します。
お客様の悩みに応える内容作り
ほとんどのホームページは、「中小企業の歴史」「事業内容」「商品ラインナップ」といった中小企業側の説明が中心になりがちです。しかし、お客様は自分の悩みを解決してくれるかどうかに関心があります。
お客様の悩みや疑問に応える内容を充実させることで、ホームページがお客様の役に立つことができるようになり、購入や問い合わせに繋がりやすくなります。
- よくある質問とその回答
- お客様の具体的な悩みを解決した事例
- 初めての方向けの基本情報
- 専門用語の分かりやすい説明
- 商品・サービス選びのポイント
このような情報は、お客様が求めている内容で、その方の困ったを解決できる役に立つ情報です。「この中小企業は私の悩みを理解してくれている。解決してくれる。」と感じてもらえれば、信頼関係の構築にもつながり、この場合も購入や問い合わせに繋がりやすくなります。
情報の整理と見つけやすさの向上
ホームページにお客様に役立つ内容が掲載されていても、お客様がスムーズに見つけられなければ目にしてもらうことができません。お客様の行動パターンに合わせて情報を整理することが大切です。
- 初めての方と検討中の方で異なる情報を提供
- お客様がよく探す情報を目立つ位置に配置
- 関連情報へのリンクを適切に設置
- スマートフォンでの見やすさ・使いやすさの確保
- わかりやすい言葉づかいと、適度な文章量
- 文章を補完する画像や動画の配置
最近は、多くのお客さまがスマートフォンでホームページを見るようになってきています。小さな画面でも見やすく、操作しやすいデザインか、スムーズに表示されるかを、自分自身のスマートフォンを使って、実際に確認することが重要です。
安心感と信頼感を高める工夫
お客様が商品やサービスを購入する際、「本当に大丈夫だろうか」「失敗しないかな」 という不安を感じることは自然なことです。その不安を解消して、安心感を提供することも大切です。
- 実際のお客様の声や体験談
- 詳細な商品・サービス情報
- 中小企業の専門性や実績の紹介
- 保証やアフターサービスの説明
- わかりやすい明確な料金体系
こういった情報は、お客様が感じている「不安」を「安心」に変える効果が期待できます。特に初めてホームページを訪問するお客様にとって、こうした情報は決断を後押しする重要なポイントになります。
より詳しいお客様理解に基づいたホームページ改善の方法については、「Webマーケティングの成功は「ユーザー理解」が重要」という記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせtご覧ください。
お客様理解がもたらす良い循環
お客様の気持ちを理解して、それに応えるホームページに改善していくと、いくつかの良い流れが生まれます。
- お客様の求める情報が充実したホームページになる
- お客様の満足度が高まり、滞在時間が長くなる
- 問い合わせや購入などの行動につながりやすくなる
- リピーターや口コミでの新規お客様が増える
- より多くのお客様の声が集まり、さらなる改善のヒントが得られる
- ホームページがさらに充実し、満足度が高まる
お客様理解を起点とした改善サイクルが回り始めると、継続してホームページへの集客できるようになります。しかし、お客様の気持ちを考えていないホームページは、いくら広告費をかけて人を集めても、その効果は期待できないでしょう。
まとめ:ホームページ成功の鍵はお客様理解にある
ホームページを通じて商品やサービスを多くの方に知ってもらい、購入や問い合わせにつなげたいと思うなら、「集客すること」と同じくらい「お客様の気持ちを理解すること」が大切です。
お客様がどんな悩みを持ち、何を知りたいと思っているのか。どのように情報を探し、何を基準に判断しているのか。こうしたことを理解した上でホームページを作り、改善していくことが、本当の意味での効果的なホームページ運営ができるようになります。
「まずは人を集めよう」ではなく、「まずはお客様を理解しよう」という考え方が、ホームページを活用した集客の取り組みであるSEOの第一歩です。
お客様理解に基づいたホームページ改善について、より詳しく知りたい方は、「Webマーケティングの成功は「ユーザー理解」が重要」という当社サイトのブログ記事をぜひご覧ください。
また、お客様理解に基づいたホームページ改善と集客をサポートするWebコンサルティングサービスもありますので、ホームページの運用、集客にお悩みの方は一度ご相談ください。
初回相談は無料です。
いつでもお気軽にご相談ください。
ご相談はこちらから