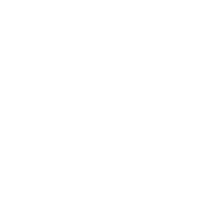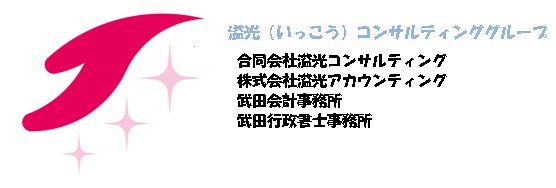「関西から日本を元気にする」
資金調達に強い税理士事務所。


代表は金融機関出身・ファイナンシャルプランニング技能士(FP1級)
現場を知るコンサルタントが御社を金融面からサポートします。
税理士事務所、行政書士事務所としての信用
税理士及び行政書士は法律で守秘義務を課せられています。
経営革新等支援機関として認定されています。
補助金や助成金の申請は支援機関との連携が不可欠です。
金融機関と税理士・行政書士事務所の両視点。
ちょっと変わった見方で幅広くお客様を支援していきます。

でも何処に何を申し込めばいいのか、必要書類って何かと面倒です。
資金の調達・銀行融資でお悩みの方。是非ご相談ください。
*借入申込に必要な決算書や試算表についても多数のご相談承ってます。
お気軽にお問い合わせください。

今、政策の後押しもあって起業しやすい環境です。
「何をどうして」「資金はどうする」「事業計画はあるけど書面には」
是非一緒に考えませんか?

*個人での開業はもちろん何かと面倒な法人設立の手続き。
*創業に必要な自己資金と資金調達。
*銀行から「事業計画書」を求められている・・・・.
*「銀行を紹介してください。」「決算書・試算表を一緒に説明して下さい。」
*会計・財務の顧問としてお付き合い。

ホームページにお越しいただき誠にありがとうございます。
当社は2014年に中小企業を資金面からサポートするために設立された融資支援を専門とするコンサルティング会社です。グループ会社には税理士事務所及び行政書士事務所を併設しております。
当社同様にクライアント様も同様に新規に事業を始めた会社様が少なくありません。会社は人、物、金で成り立っているといわれます。特にお金(資金)の問題は経営者様にとって深刻な問題です。銀行借入が多額に上る会社であれば、利益は出ているのに全く通帳残高が増えないというp一見奇妙な現象すら起こりえます。これらの中には会計の理解があれば十分に予測でき、また対処することも可能な事案が少なくありません。
しかしながら、多くの税理士事務所、会計事務所は日々の帳簿付けと税金計算を生業とし、クライアントの資金繰りやキャッシュフローの改善策や銀行等とのパイプを持ち合わせておりません。
永続的な経営にはキャッシュフロー経営が欠かせません。当事務所が御社の資金繰り及び永続的な経営に多少なりとも寄与できる機会を頂けましたら幸いです。
『アメリカの企業でいわゆる「株主第一主義」を修正。』
先日、こんな記事がありました。
この記事によると、アメリカの主要企業経営者団体が「株主第一主義」を見直し、
従業員や取引先、地域社会などの利益を尊重した経営に取り組む、と声明をしたとのこと。
従来の株価上昇や配当増加などの、株主の利益を優先してきた行動指針に対する批判をかわす目的とも捉えられます。
修正内容は具体的には(1)~(5)順番に
(1)顧客(2)従業員(3)取引先(4)地域社会(5)株主
となっており全利害関係者への声明とされてます。
「会社は誰のものか」という議論も久しくされています。決して株価上昇目的は否定されることではありません。
声明の目的はどうであれ、一石を投じた形となって長期的な事業発展に貢献されればいいと思います。
今までの株主第一主義から修正され、企業の行動指針が変化するに伴い財務指標は変化していく可能性があります。
従来よりの株主第一主義の主たる指標であるROE(自己資本利益率)。
ちなみにROEとは・・・=「当期純利益/自己資本」
自己資本1単位に対していくら利益が出ているかを表していて、
株主から見ると自己資本利益率が高い会社は投資した資金で効率よく利益を出してくれている会社であると判断できますので投資が集まりやすく株価が上昇につながります。
よってROEを高めるには、「分子の当期純利益を向上」させるか、「分母である自己資本を圧縮」するかになります。
株主第一主義のもとでは、ROE向上や株主還元に好影響となる財務戦略が行われます。
例えば余剰資金での自社株購入(自己資本の圧縮)もその一つだと考えられます。
実際、ROE重視の経営姿勢が高株価を呼び、株主の要求にも財務戦略としてROE目標が掲げられるようです。
では声明にある新たな行動指針のもとでは、どのような財務指標が注目されるようになって、伴って変化していくと予想されるでしょう。
以下私見ですが・・。
(2)従業員・・・公正な報酬の支払いや福利厚生の提供。
容易に予想されるのが適正な人件費や福利厚生費。
単純に金額が高いという事ではなく、付加価値(売上総利益)に占める人件費比率である労働分配率が「いかにあるべきか企業独自の戦略」をもって取り組んでいるかに注目されるでしょう。
(3)取引先・・・規模の大小を問わず良きパートナ-として扱う
取引先との関係を財務指標としてあらわすのには様々な見方があって、一概には言えません。
支払債務(買掛金や未払金)の項目に着目して、
例えば、取引上優位な地位を利用して下請けに支払サイクルの延長など負担をシワ寄せをすると、
貸借対照表の買掛金や未払金の残が仕入や経費の増加に比して不当に増加します。
仕入値引の不当な増加も、損益計算書に見えてくることもあるかもしれません。
一方、支払サイクルの長期化短縮化は企業努力や業界の環境、売上サイト(売上から入金までの期間)とのバランスにも影響しますから短絡的な判断はできません。
いずれにしても業界の指標や「損益計算書」上の仕入経費の増減と「貸借対照表」の買掛金や未払金の増減のバランスとが不合理であれば、
それらが取引先の利益を害する自社の利己的な利益の追求によるものであるかを見極める必要があります。
また今後は、ROE向に向かっていた余剰資金が買掛金や未払金の圧縮に向かう財務戦略も有りうることかもしれません。
(2)(3)以外の
(1)顧客・・・顧客の期待にこたえてきた伝統を前進させる。
(4)地域社会・・・持続可能な事業運営で環境を保護する。
SDGsとして馴染みがあることでしょう。
(1)(4)ついては専門的な研究が進んでいるようですが、深入りせず割愛いたします。
常に投資家の目にさらされている上場企業・大企業のみならず、
中小企業の行動指針や思いが財務の数字に表れることに注目して金融機関や投資家が判断される材料になれば
興味深いことかもしれません。
ただもっと言えば財務指標を表に立たせて、良かれと思われる行動指針をアピールする。
そんな本末転倒なことは・・・ないように。
です。
大きな客船を見ては、何で海に浮くんだとか、悠然と雲の合間を直進する飛行機を見ては、何で空に浮くんだとか、
小さい頃の不思議がいまだに思い出されます。
海や空に浮かぶ、その勇壮で不思議な姿も、はじめから「姿」を重視したのではなく、その求められる働きを追及する為の「技術」を駆使した結果として、その最適な「姿」の現れだと聞いたことがあります。
あの「姿」は作り手として本来の「智と技との賜物」なのだということです。
企業の経営や財務体質の健全性を思わせる「姿」として、代表的なものに
自己資本比率、最近では株主の要望が強く求められる自己資本利益率(ROE)などがあります。
どちらも、数値を追い求めるには充実した利益と、企業の資産を有効活用することが求められ、そうして「健全な姿」として目に映ることになります。
当然ながら一朝一夕にその「姿」が実現できることではなく、その「姿」ありきで経営するものでもなく。
1つの目標として掲げて、
企業の人材、経営努力、企業としての姿勢が表に現れた、「結果として」の「姿」が最善の姿であるべきです。
さて
数年後、1万円札の肖像が渋沢栄一氏にリニューアルされる予定で、
「論語と算盤」には「道理に合った利潤」という理念が底流しています。
道理にかなわない利潤や、財務の数値のみの小手先の操作で映し出された「姿」。
そのような一見健全そうな「姿」には、
どうも勇壮でもなく、どこか危なっかしさを感じるかもしれません
そう
海に浮かんだり、空の雲の間に浮かんだり・・・・・出来そうもないでしょうか。
お客様の通帳を見る機会が多くあります。
何気なく見ていると違和感があって
三菱UFJ.三井住友、などメガバンクでは
右側に「預入」左側に「払出」、となってます。
一方、金融機関除く民間は逆で、
その銀行の通帳を記帳する際、預入は左側(資産側の増加)払出は右側(資産側のマイナス)にします。
記帳する立場からはややこしく思う方もおられるかもしれません。
何故なのだろうかと。
銀行自体のバランスシート(貸借対照表)は通帳の表示通りなのです。
つまり銀行にとって預金者からの預入は負債ですから右側、払出は逆なので左側に、通帳はその通り記載されているとすれば、バランスシートの記載する立場の違いなのだろうと思います。
ちなみに
ゆうちょは上記の逆で、民間と同じ通帳の預入は左側に、払出は右側に記載されてます。
記載の仕方が異なるについては、それぞれの立場があっての事。
銀行も記帳の目的には変わりないことですし、
ご自身の通帳見て取引や残高なりに変わりはありません。
鏡を見て、右手を動かしてみると写る左手が動いている様に見えます。
貸し手は借り手の立場を思い、借り手は貸し手の立場を思う。
相手の立場が逆である事を分かっていれば
何か分かる事と、自身の立場を見直す事も大いにあるはずです。
『リスク』のあることにはどちらかというと出遭いたくありません。
感覚的には、『リスク』というと
・持っていた株価が下がった。
・事業で投資したけど思うような収益が上がらなかった。
よく保険を事業に対してのリスクマネジメントという言葉を使う場合には
・死亡や傷病などで事業主の経営参加に支障が出る状態
その他、日常的にも使うことも多いですね。
どちらかというと将来に想定される「マイナス」のイメージでしょう。
経済の意味合いで言うと少し違っています。
実現される価値が期待される価格が「上がっても下がっても」『リスク』と言っています。
例えば
100円の株を購入して110円になることを期待してます。
90円になってしまうかもしれません。
また130円になるかもしれません。
この場合「130円になるかもしれない」ことも『リスク』と意味付けします。
『リスク』の大きさは?というと
100円になってしまうかもしれませんし120円になるかもしれません、という場合は、
130円になる場合と比べてより『リスク』は「低い」と考えます。
つまり「期待される価値より『ブレル幅』の大小が『リスク』の大きさ」という尺度です。
13:00に待ち合わせしてます。相手が13:30に遅れることはいわゆる『リスク』ですが
12:30に来られても怒られそうで『リスク』です。
13:00前後に来ることを期待(予定で)して用意する訳ですから。
どれだけ早く(遅く)来ることまで期待(許容)すればいいんでしょう・・・
これが『リスク』という感覚でしょうか。
この『リスク』。
統計学での言葉では『分散』(その平方根が『標準偏差』)というもので数値化します。
(データの平均値と、各々のデータとの差の大きさを一定の数式で計算)
株価予測・様々な投資商品・企業行動・・・。実際に駆使されています。
身近な例では受験の際の「偏差値」もそうでした。
実際に起こり得るモノゴトが期待される値や事象との『ブレル範囲』をいかに認識するか。
経済、経営、市場だったり相手のあることですから容易ではありませんが、リスクを避けて通れない場合やリスクをあえて許容する場合も当然あります。
期待する範囲を大きくブレる際にどう行動するかをあらかじめ想定しておく事、
そのリスクを測れる数値化技術とともに、感覚を研ぎ澄ます必要も重要だと思います。